
「飲みすぎた翌朝、頭痛・吐き気・むくみで最悪…」
「仕事があるのに二日酔いがキツい…」



「飲みたいけど二日酔いにならないよう事前に対策したい…」
そんな時、市販の漢方薬を上手に活用すれば、つらい症状を軽減することが期待できます!
👉 この記事を読めば、翌朝の不快感を軽減し、快適に目覚める手助けになる方法がわかります!
二日酔い対策におすすめな市販の漢方薬とは?|選び方と効果を徹底解説
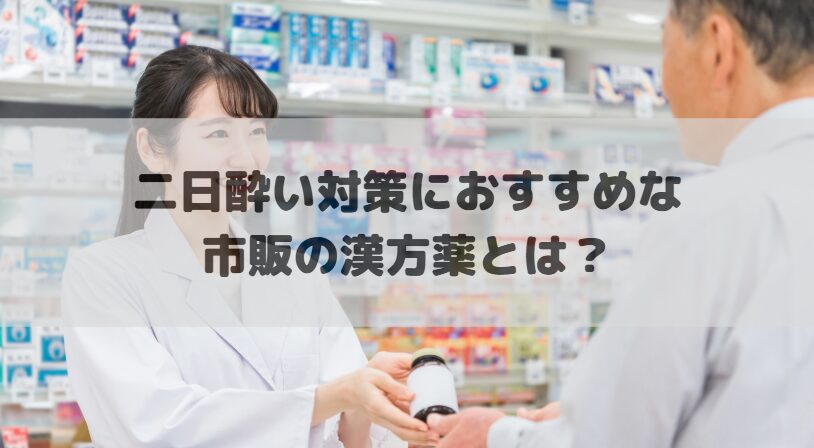
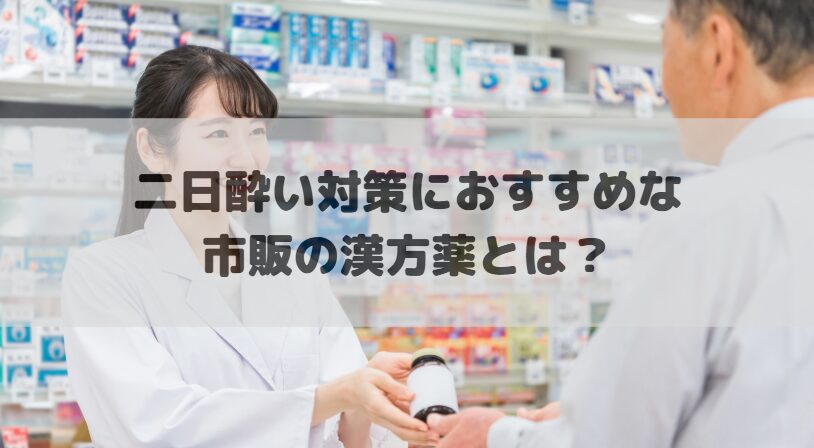



二日酔いの頭痛や吐き気、むくみをどうにかしたい…
市販の漢方薬をうまく活用すれば、そんな悩みをスッキリ解決できるかもしれません!
今回は、二日酔いに最適な漢方薬の選び方と、その効果について徹底解説します。
✔ 市販の漢方薬を選べば、二日酔い症状を緩和!
✔ 症状別にピッタリな漢方薬を選べる!
✔ 漢方薬を上手に活用すれば、翌朝に快適な状態で目覚める手助けになる!
💊 市販の漢方薬で二日酔いが改善する可能性がる理由



市販の漢方薬で本当に二日酔いが治るの?
そんな疑問を持っているあなたに、漢方薬がどのように二日酔いを改善するのか、その仕組みを簡単に説明します。
✅ 漢方薬が二日酔いにアプローチする理由
- 体内の余分な水分を排出
漢方薬には、体にたまった余分な水分を排出する効果があるものが多く、むくみや頭痛を軽減できます。 - 肝機能をサポート
アルコールが分解される際、肝臓が重要な役割を果たします。
肝機能をサポートする漢方薬を使うことで、アルコールの分解を促進します。 - 血行促進&疲労回復
漢方薬は血行を改善し、身体の回復を助けるため、二日酔いによるだるさや倦怠感を軽減します。
📌 ポイント
- 市販の漢方薬は、自然成分で体に優しく、二日酔いの症状を緩和する効果があります。
- 特に、むくみや吐き気に悩む場合、体質に合った漢方薬を選ぶことが大切です。
🔑 漢方薬の効果的な使用方法



どの漢方薬を選べば、二日酔いを早く解消できる?
漢方薬の効果的な使用方法、自分の体調や症状に合ったものを選ぶことが大切です。
正しい選び方を理解して、効果的に使用していきましょう!
✅ 二日酔い対策に適した漢方薬選びのポイント
- 自分の症状を把握する
- むくみがひどい場合:水分の排出を促進する漢方薬(例:五苓散)
- 頭痛や吐き気がひどい場合:血行促進や肝機能をサポートする漢方薬(例:茵陳蒿湯)
- 飲み会前後に服用タイミングを工夫する
- 飲み会前に飲む:予防効果を高めるために、早めに服用しておく
- 飲み会後に飲む:二日酔いの症状が出始めたタイミングで服用すると効果的
- 継続的に服用する
- 一度の服用で劇的に改善されない場合でも、継続的に服用することで徐々に効果が現れることが多いです。
📌 ポイント
- 自分の体調と症状に合わせた漢方薬を選ぶことで、効果的に二日酔いを防止・解消が期待できます。
- 服用タイミングを意識することで、漢方薬を効果的に使用することができます。
💡 二日酔いの症状別、適した漢方薬を選ぶ方法



二日酔いの症状って人それぞれ。自分にはどんな漢方薬が合うのか知りたい!
二日酔いの症状に合わせた漢方薬を選ぶことで、効果的に症状を緩和できます。
以下の表を参考に、症状別に適した漢方薬を選びましょう!
✅ 症状別にオススメの漢方薬
| 症状 | おすすめの漢方薬 | 効果 |
|---|---|---|
| 頭痛や吐き気がひどい | 五苓散(ごれいさん) | 体内の余分な水分を排出し、頭痛や吐き気を緩和 |
| 肝機能が低下していると感じる | 茵陳蒿湯(いんちんこうとう) | 肝臓をサポートし、アルコールの分解を助ける |
| むくみやだるさがひどい | 防已黄耆湯(ぼういおうぎとう) | むくみ体質を改善し、体内の余分な水分を排出 |
| 飲み過ぎ後、顔が赤くなる | 黄連解毒湯(おうれんげどくとう) | 体内の熱を冷まし、赤みやむくみを抑える |
📌 ポイント
- 症状別に漢方薬を選ぶことで、効果的に二日酔いを予防・解消が期待できます
- 自分の体質や症状に合わせて漢方薬を選ぶと、翌朝に快適な状態で目覚める手助けになります
二日酔いに効く市販の漢方薬5選|おすすめの市販薬とは?
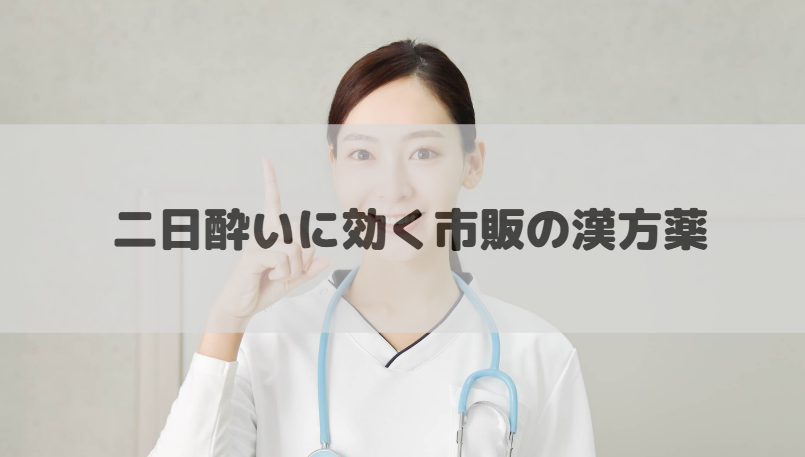
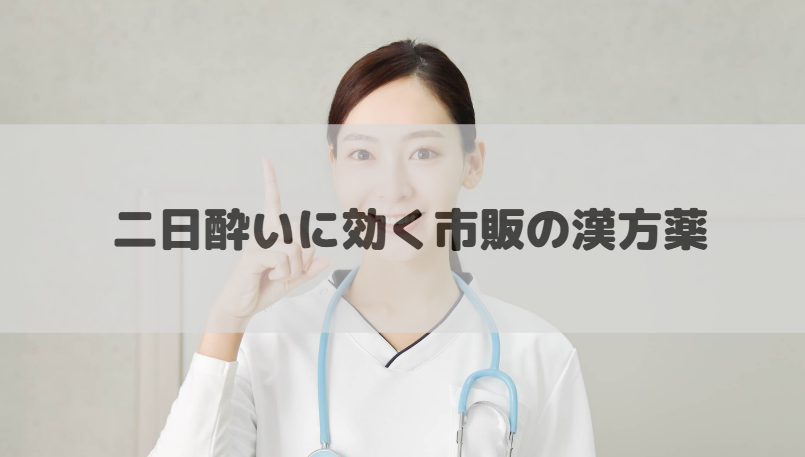
二日酔いに悩んでいる方には、市販の漢方薬が頼りになります。漢方薬は、体に優しく症状を和らげるだけでなく、根本的な体調改善にも効果的です。
ここでは、二日酔いに効くとされる市販の漢方薬5選をご紹介します。
自分の症状に合ったものを選ぶことで、早期の回復を期待できます。
① 五苓散(ごれいさん):むくみ・頭痛・吐き気に効く万能薬
五苓散(ごれいさん)は、むくみや頭痛、吐き気といった二日酔いの代表的な症状に効果的です。
アルコールが体内で水分を停滞させるため、これを解消する力を持つ五苓散は、特に体内の余分な水分を排出する働きに優れています。
五苓散の効果
- むくみ解消:体内の余分な水分を排出し、むくみを軽減
- 頭痛の緩和:頭部の血流を改善し、痛みを和らげる
- 吐き気の抑制:胃腸を整え、吐き気や胸やけを軽減
📌 ポイント
- 二日酔いによる浮腫や頭痛、吐き気に幅広く対応する万能薬。
- 特に水分が溜まりやすい体質の人にオススメ。
② 茵陳蒿湯(いんちんこうとう):肝機能サポートでアルコールの代謝を促進
茵陳蒿湯(いんちんこうとう)は、アルコールが肝臓で代謝される過程をサポートする漢方薬です。
肝機能を強化し、アルコールの解毒を助けるため、二日酔い後の回復を早めてくれます。
茵陳蒿湯の効果
- 肝機能のサポート:肝臓を助け、アルコールの分解を促進
- 消化促進:胃腸の働きを整え、二日酔い後の不快感を軽減
- 疲労回復:体内の老廃物を排出し、疲れを取る
📌 ポイント
- アルコールを頻繁に摂取する方や、肝臓の負担が気になる方にオススメ。
- 体内の老廃物を効果的に排出する力があり、翌日スッキリ目覚めたい方に最適。
③ 黄連解毒湯(おうれんげどくとう):体の熱を冷まして、アルコール由来の炎症を抑える
黄連解毒湯(おうれんげどくとう)は、体内にたまった熱を冷まし、炎症を抑える効果があります。
アルコールによって体温が上昇し、顔の赤みや炎症を引き起こすことがありますが、黄連解毒湯はそれを緩和します。
黄連解毒湯の効果
- 体の熱を冷ます:アルコール由来の体温上昇や炎症を鎮める
- 消炎作用:二日酔いによる不快感を軽減
- 肝臓の浄化:肝臓の解毒作用を助け、アルコールの代謝を促進
📌 ポイント
- 顔が赤くなる、のぼせるなど、体内の熱を感じる方にオススメ。
- 炎症を抑えつつ、体内をクールダウンさせたい時に有効。
④ 猪苓湯(ちょれいとう):尿の排出を促進し、むくみや体の重さを解消
猪苓湯(ちょれいとう)は、尿の排出を促すことで、二日酔いのむくみや体の重さを軽減する漢方薬です。
特にむくみやすい体質の方に最適で、余分な水分を速やかに体外に排出します。
猪苓湯の効果
- 尿の排出促進:むくみや体の重さを解消
- 消化促進:胃腸の働きを助け、消化不良を改善
- 疲労回復:体内の余分な水分を取り除き、スッキリとした体調に
📌 ポイント
- むくみがひどい、体が重いと感じる方にオススメ。
- 尿の排出を促進することで、体内の不要なものを取り除き、スッキリした気分を取り戻す。
⑤ 防已黄耆湯(ぼういおうぎとう):むくみやすい体質の改善に最適
防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)は、むくみやすい体質の改善に効果的な漢方薬です。
二日酔いによる体内の余分な水分を排出するだけでなく、むくみを予防し、体調を整える効果もあります。
防已黄耆湯の効果
- むくみ予防:余分な水分を排出し、むくみを改善
- 体調を整える:免疫力を高め、体調のバランスを整える
- 疲れを軽減:二日酔いのだるさや重さを解消
📌 ポイント
- むくみが気になる方、体質的にむくみやすい方にオススメ。
- 疲れを軽減し、二日酔いをすっきり解消したい方に最適。
市販の漢方薬の効果的な使い方|二日酔いを早く治すためのタイミング
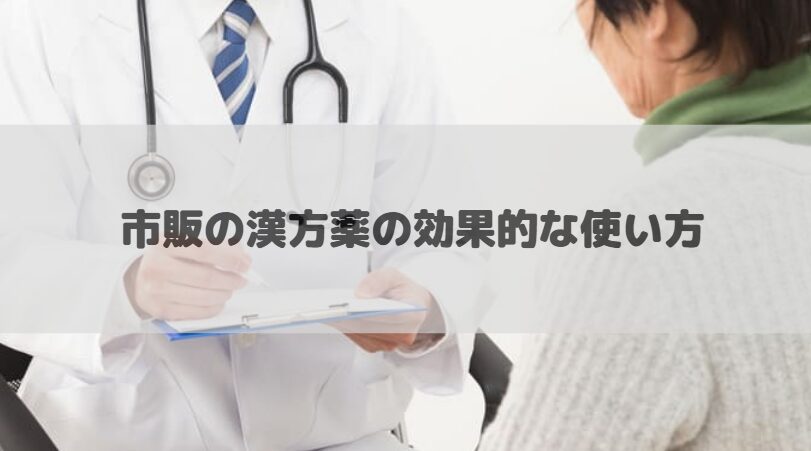
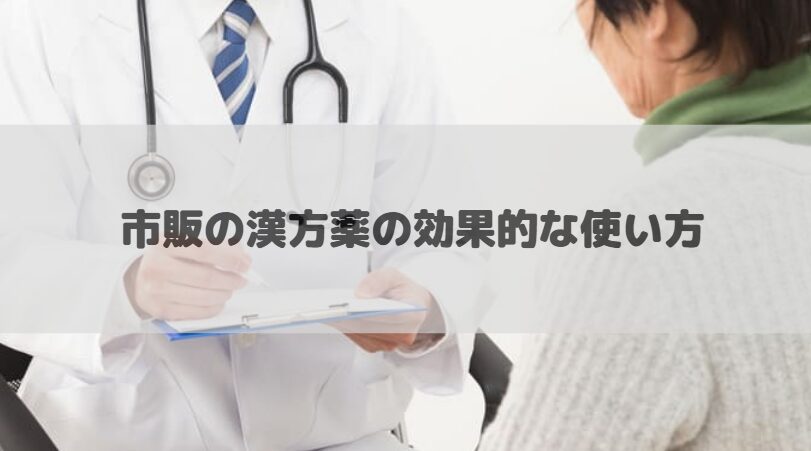



二日酔いの頭痛や吐き気、むくみを今すぐなんとかしたい…
そんなとき、漢方薬の正しい使い方を知っていれば、回復スピードが格段に違います!
✔ 飲み会前・後の服用タイミングを意識するだけで、二日酔いのダメージを最小限に!
✔ 即効性の高い漢方薬を活用すれば、翌朝スッキリ目覚められる!
✔ 漢方薬+生活習慣の見直しで、二日酔いしにくい体質づくりも可能!
ここでは、市販の漢方薬を最大限に活かす服用タイミング&効果的な活用法を徹底解説します!
🕰 飲み会前・飲み会後の服用タイミングを徹底解説!
「二日酔いになってから漢方薬を飲む」よりも、飲み会前から準備をしておくことで、翌朝の不快感を大幅に軽減できます。
📌 飲み会前に服用するべき漢方薬
✔ 五苓散(ごれいさん) → 体の水分バランスを整え、むくみ・頭痛を予防
✔ 茵陳蒿湯(いんちんこうとう) → 肝機能をサポートし、アルコールの分解を助ける
📌 飲み会後に服用するべき漢方薬
✔ 黄連解毒湯(おうれんげどくとう) → 体の熱を冷まし、炎症を抑えて頭痛・吐き気を軽減
✔ 猪苓湯(ちょれいとう) → 尿の排出を促し、むくみや体のだるさをスッキリ解消
📌 ポイント
- 飲み会前は「予防」目的で服用し、飲み会後は「回復」目的で服用!
- 特に、肝臓の負担を減らす漢方薬は飲み会前に飲んでおくと◎!
⚡ 即効性を求めるなら、どの漢方薬がベスト?



とにかく今すぐ二日酔いを解消したい…!
そんなときにおすすめの即効性が高い漢方薬をご紹介します。
✅ すぐに効く漢方薬3選
| 症状 | おすすめの漢方薬 | 効果 |
|---|---|---|
| むくみ・頭痛・吐き気がひどい | 五苓散(ごれいさん) | 体内の余分な水分を排出し、むくみ・頭痛・吐き気を緩和! |
| アルコールが抜けず、倦怠感が強い | 茵陳蒿湯(いんちんこうとう) | 肝臓の機能をサポートし、アルコールの分解を促進! |
| 顔が赤くなりやすい・のぼせる | 黄連解毒湯(おうれんげどくとう) | 体内の熱を冷まし、アルコールによる炎症を鎮める! |
📌 ポイント
- すぐに効果を実感したいなら、「五苓散」や「黄連解毒湯」が◎!
- 肝臓の回復を早めたいなら、「茵陳蒿湯」がおすすめ!
🌿 漢方薬を飲んだ後に試すべき生活習慣
漢方薬を飲むだけで終わりにせず、回復を加速させるための生活習慣も取り入れると、より効果的に二日酔いを解消できます。
💧 水分補給をしっかりと!
✔ スポーツドリンク+水で電解質を補給
✔ アルコールの分解を助けるため、こまめに水分を摂る
✔ コーヒーや緑茶はカフェインの利尿作用があるためNG
🏃 軽い運動やストレッチで血流促進!
✔ 軽い散歩をするだけでも、血流が良くなり回復スピードがUP
✔ 肩・首を回すストレッチで血流を改善し、頭痛を軽減
🍲 栄養を摂って体を整える!
✔ シジミの味噌汁でオルニチン補給&肝臓をサポート
✔ 消化に良いお粥やスープで胃腸を整え、体に優しくエネルギーチャージ
📌 ポイント
- 水分補給+軽い運動+栄養摂取を意識することで、二日酔いからの回復が早くなる
- カフェインは脱水を促進するため、控えるのがベター
✅ 飲み会前・後の服用タイミングが重要
→ 五苓散・茵陳蒿湯は「予防」、黄連解毒湯・猪苓湯は「回復」目的で服用
✅ 即効性を求めるなら?
→ むくみ&頭痛には「五苓散」、肝臓ケアには「茵陳蒿湯」、のぼせ対策には「黄連解毒湯」
✅ 漢方薬+生活習慣で、回復を加速
→ 水分補給・軽い運動・消化に良い食事を意識
二日酔いに市販の漢方薬を取り入れる前に知っておくべき注意点
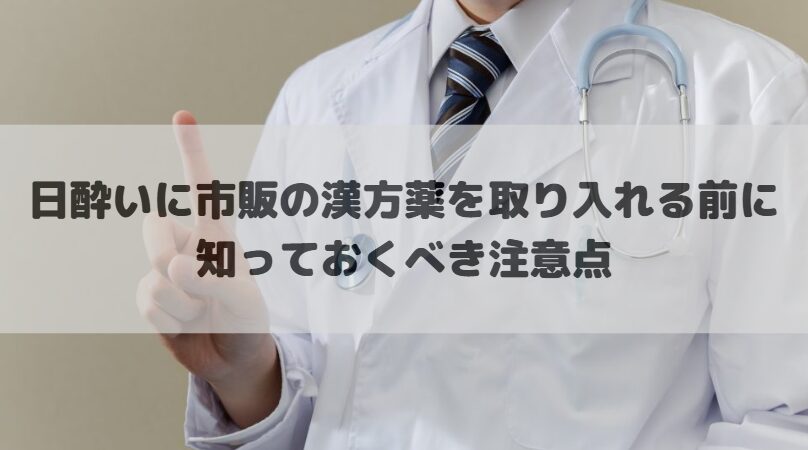
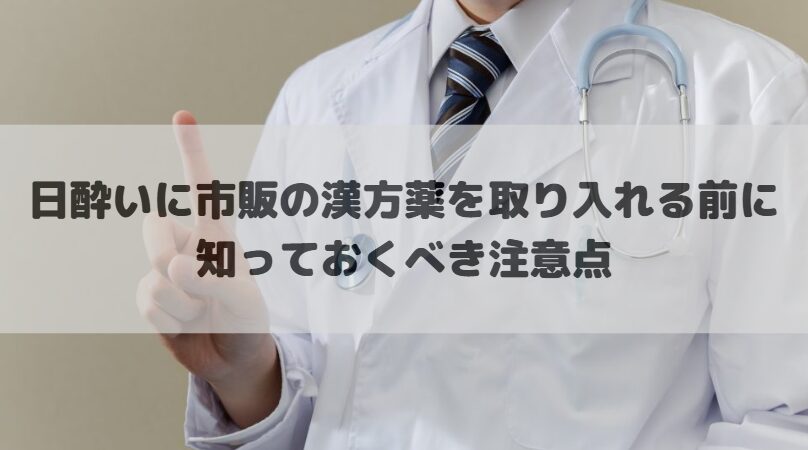



二日酔い対策に漢方薬を使ってみたいけど、安全に飲めるのか心配…
市販の漢方薬は体に優しく、二日酔いの症状を和らげる効果が期待できますが、正しい使い方をしなければ十分な効果が得られなかったり、副作用が出る可能性もあります。
✔ 漢方薬には副作用がある場合も!体質に合わないと不調の原因に?
✔ 他の薬との飲み合わせに注意しないと、効果が相殺されることも!
✔ 「飲んだけど効かない…」そんなときに試すべき対処法とは?
ここでは、二日酔い対策に漢方薬を取り入れる際の注意点について詳しく解説します。
⚠ 漢方薬の服用で注意すべき副作用とは?
「漢方薬は自然由来だから、副作用はないのでは?」と思われがちですが、体質や服用量によっては、副作用が出る場合もあります。
✅ 漢方薬による副作用の可能性
- 胃腸の不調 → 体質によっては、胃もたれ・下痢・吐き気を感じることも
- アレルギー反応 → まれに漢方薬の成分にアレルギーを持つ人もいる
- のぼせ・ほてり → 体を温める作用がある漢方薬では、のぼせることも
- むくみの悪化 → 水分代謝に影響を与える漢方薬を誤って飲むと、逆にむくむ場合も
✅ 副作用を避けるためのポイント
✔ 初めて服用する場合は、少量から試す
✔ 空腹時の服用は避け、胃への負担を軽減する
✔ 漢方薬も薬の一種!体質に合わない場合、副作用が出ることもあるので注意
✔ 特にアレルギーや持病がある人は、事前に成分を確認
✔ 異変を感じたらすぐに服用を中止し、医師・薬剤師に相談
💊 他の薬と併用する際の注意点



頭痛薬や胃薬と一緒に飲んでも大丈夫?
漢方薬は比較的安全とされていますが、他の薬と併用する際には注意が必要です。
✅ 漢方薬と他の薬の組み合わせで気をつけるべきこと
- 成分が重複する可能性
→ 例えば、「五苓散」と「むくみ改善薬」を併用すると、必要以上に水分が排出され、脱水症状になることも - 薬の効果を打ち消す場合がある
→ 「黄連解毒湯」などの解毒作用がある漢方は、他の薬の吸収を妨げることがある - 肝臓への負担が増加することも
→ 肝機能をサポートする漢方薬と、肝臓に負担をかける薬(鎮痛剤・解熱剤など)を同時に摂取すると、肝臓に過度な負担をかける可能性がある
✅ 併用する際の注意点
✔ 同じような効果を持つ薬を重複して飲まない
✔ 服用時間をずらし、吸収を妨げないようにする
✔ 持病がある人・処方薬を服用中の人は、必ず医師・薬剤師に相談
📌 ポイント
- 自己判断で市販の漢方薬を他の薬と併用すると、思わぬ副作用が出ることも!
- 他の薬との飲み合わせに不安がある場合は、専門家に相談するのがベスト!
🤔 効果がない場合の対処法



二日酔い対策で漢方薬を飲んだけど、全然効かない…
そんなときは、いくつかのポイントを見直すことで、効果を実感できる可能性があります。
✅ 漢方薬の効果を感じない原因と対処法
| 原因 | 対処法 |
|---|---|
| 服用のタイミングが間違っている | 飲み会前に「予防目的」で飲むのか、二日酔い後に「回復目的」で飲むのかを見直す! |
| 体質に合っていない | 体質や症状に適した漢方薬を選び直す!(例:むくみがひどいなら「五苓散」、胃が弱いなら「茵陳蒿湯」) |
| 服用量が適切でない | 市販薬の推奨量を守る!少なすぎると効果が感じにくいことも |
| 生活習慣の影響で効果が出にくい | 水分補給や適度な食事など、漢方薬と併用して生活習慣も見直す! |
✅ 効果を高めるために試すべきこと
✔ 症状に合った漢方薬を選び直す!
✔ 服用のタイミングを見直す!(飲み会前・飲み会後)
✔ 食事・水分補給・適度な運動と組み合わせて、回復を早める!
📌 ポイント
- 漢方薬の効果は即効性ではなく、体質や症状に合っていないと効かないことも!
- 「効かない」と思ったら、服用のタイミングや生活習慣を見直そう!
✅ 漢方薬にも副作用がある
→ 体質に合わない場合、胃の不調・のぼせ・アレルギーなどが起こることも
✅ 他の薬との併用は慎重に
→ 成分の重複・効果の相殺・肝臓への負担を避けるため、事前に確認が必要
✅ 「効かない」と感じたら、服用のタイミングや生活習慣を見直す
→ 飲み会前に予防的に飲むか、飲み会後に回復目的で飲むかを明確にすることが大切
まとめ|市販の漢方薬で二日酔いをスッキリ解消!正しい使い方を身につけよう



「二日酔いで朝から最悪な気分…」
「仕事があるのに体が重くて動けない…」
そんな二日酔いの不快感をスピーディに解消するためには、自分に合った市販の漢方薬を選び、正しい使い方をすることが大切です。
✔ 二日酔いの症状に合った漢方薬を選ぶことで、より効果的に回復!
✔ 飲み会前・飲み会後の服用タイミングを工夫して、ダメージを最小限に!
✔ 生活習慣を見直せば、そもそも二日酔いになりにくい体質へ!
ここでは、市販の漢方薬を活用するためのポイントを総まとめします!
🔍 自分に合った市販の漢方薬を見つける方法



どの漢方薬を選べばいいかわからない…
そんな方のために、二日酔いの症状別に最適な市販漢方薬の選び方を解説します!
✅ 症状別・おすすめの漢方薬
| 症状 | おすすめの漢方薬 | 効果 |
|---|---|---|
| むくみ・頭痛・吐き気がひどい | 五苓散(ごれいさん) | 体の余分な水分を排出し、むくみや頭痛を軽減! |
| 肝臓の負担を減らしたい | 茵陳蒿湯(いんちんこうとう) | 肝機能をサポートし、アルコールの分解を促進! |
| 顔が赤くなりやすい・のぼせやすい | 黄連解毒湯(おうれんげどくとう) | 体の熱を冷まし、炎症を抑えてのぼせを軽減! |
| 体がだるい・重くて動けない | 猪苓湯(ちょれいとう) | 尿の排出を促進し、むくみや体の重さを解消! |
| むくみやすい体質を改善したい | 防已黄耆湯(ぼういおうぎとう) | 体の水分バランスを整え、むくみにくい体質を作る! |
✅ 市販の漢方薬を選ぶときのポイント
✔ 症状に合ったものを選ぶ(むくみ・倦怠感・頭痛など)
✔ 「予防目的」or「解消目的」を明確にする(飲み会前 or 飲み会後)
✔ 市販薬はドラッグストアやオンラインで購入できる
🚀 二日酔い防止と解消のために実践すべきこと



漢方薬だけじゃなく、もっと効率的に二日酔いを防ぎたい!
そんな方は、日頃の生活習慣を少し意識するだけで、二日酔いの予防&回復スピードをUPできます!
✅ 二日酔いを防ぐためにできること(飲み会前の準備)
✔ 「五苓散」「茵陳蒿湯」を飲み会前に服用し、予防する!
✔ お酒を飲む前に「シジミの味噌汁」や「納豆ご飯」で肝臓をサポート!
✔ 「お酒1杯+水1杯」のルールを決めて、脱水を防ぐ!
✅ 二日酔いを早く解消するためにできること(飲み会後のケア)
✔ 「黄連解毒湯」「猪苓湯」を飲んで、体の熱&むくみを解消!
✔ 寝る前に「スポーツドリンク+水」で電解質を補給!
✔ 足を少し高くして寝ると、翌朝のむくみが抑えられる!
✅ 二日酔いになりにくい体を作るためにできること(普段の習慣)
✔ 塩分&糖分を控え、カリウム豊富な食事(バナナ・トマト)を意識!
✔ 適度な運動+ストレッチで、血行促進&むくみ解消!
✔ 水分補給の習慣をつけ、こまめに水を飲む!
📌 ポイント
- 「飲み会前の準備」+「飲み会後のケア」+「普段の習慣改善」の3ステップで、二日酔い知らずの体に!
- 漢方薬+生活習慣の改善をセットで実践すれば、翌朝のスッキリ感が段違い!
参考文献
公的機関・専門機関のウェブサイト:
厚生労働省:eJIM(日本統合医療学会)https://www.ejim.ncgg.go.jp/public/herbs/index.html
国立健康・栄養研究所:「健康食品」の安全性・有効性情報 https://hfnet.nibiohn.go.jp/
日本漢方生薬製剤協会
日本産婦人科学会、日本産科婦人科内視鏡学会、日本女性医学学会(旧日本更年期医学会):https://www.jsog.or.jp/
学術論文データベース:
PubMed:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
Google Scholar: https://scholar.google.co.jp/
書籍:
漢方に関する書籍
- 例:「漢方医学」, 「和漢薬の事典」, 「漢方薬・生薬活用QA」など
薬膳に関する書籍
- 例:「薬膳・漢方検定公式テキスト」, 「薬膳レシピ」など
キノコに関する書籍(茯苓はキノコの一種であるため)
免責事項
本記事は、漢方やメンタルケアに関する一般的な情報を提供するもので、医師の診断・治療に取って代わるものではありません。個々の症状や体質には個人差があり、必ずしも同じ効果が得られるとは限りません。体調に異変を感じた場合は自己判断せず、速やかに医療機関にご相談ください






