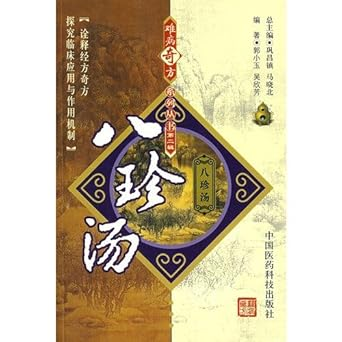「スキンケアを頑張っているのに、肌の調子が整わない…」
「もっと内側から美容ケアをしたい!」
そんな悩みを持つ方におすすめなのが、漢方の考え方です。
漢方では、巡りやバランスを意識しながら、美容をサポートする方法が古くから親しまれています。
スキンケアだけではカバーしきれない部分を、食事やライフスタイルの調整と組み合わせながらケアするのがポイントです。
本記事では、肌がきれいになる漢方の基本的な考え方や、おすすめの種類、効果的な取り入れ方を詳しく解説!さらに、日常の食事やスキンケアと組み合わせるポイントもご紹介します。
外側と内側からのWアプローチで、無理なく続けられる美容習慣を見つけましょう!
肌がきれいになる漢方の考え方|内側から整えるアプローチとは?





「スキンケアを頑張っているのに、肌の調子がいまいち…」
そんな悩みを持つ方も多いのではないでしょうか?
外側からのケアだけでなく、内側からのアプローチも意識することで、よりバランスの取れた美容習慣を目指せるかもしれません。
そこで注目されているのが、肌のコンディションを意識した漢方の考え方です。
漢方では、「巡り」「バランス」「内側からの整え方」を大切にし、日常のライフスタイルと組み合わせながら活用することがポイントとされています。
まずは、肌のために巡りを意識することがなぜ大切なのか、詳しく見ていきましょう。
肌がきれいになる漢方の基本|巡りを意識したケアが大切な理由





「肌の調子が変わりやすい」
「乾燥やくすみが気になる」
その原因のひとつに、巡りの乱れが関係していることがあります。
✅ 漢方における「巡り」と肌の関係
漢方では、肌のコンディションを整えるために「気・血・水(き・けつ・すい)」のバランスが重要と考えられています。
| 要素 | 特徴 | 肌との関係 |
|---|---|---|
| 気(き) | 活力をめぐらせる | 巡りを意識することで、バランスの良い肌状態を目指す |
| 血(けつ) | 栄養を届ける | 肌のすこやかさを意識するために、巡りを整える |
| 水(すい) | 体内の水分バランス | 肌のうるおいを意識したケアにつながる |
📌 ポイント
- 巡りを整えることで、肌のコンディションを意識しやすくなる
- 「気・血・水」のバランスを考えながら、無理なく続けることが大切
👉 漢方の考え方を取り入れながら、肌の巡りを意識する美容ケアを実践してみましょう!
肌の調子を整えるには?肌がきれいになる漢方の視点で考えるケア方法



「肌のために何をすればいいかわからない…」
そんな方は、毎日の習慣を見直すことが大切です。
漢方の視点では、スキンケアだけでなく、食事・睡眠・ストレス管理といったライフスタイル全体が肌の調子に影響すると考えられています。
✅ 肌がきれいになる漢方的ケアのポイント
✔ 巡りを意識した食生活を取り入れる
✔ 睡眠のリズムを整え、休息の時間を確保する
✔ ストレスを溜め込まない生活を意識する
✔ スキンケアと組み合わせて、外側と内側の両方からアプローチする
📌 食生活のポイント
- クコの実や白きくらげを使った美容スープを活用
- 温かいハーブティーを飲むことで、巡りをサポート
- バランスの良い食事を意識し、無理のない範囲で整える
👉 日常の習慣を少しずつ見直すことで、肌の調子を意識しやすい状態を目指せるかもしれません!
肌がきれいになる漢方を活用するために、ライフスタイルで意識したいこと



漢方を取り入れるなら、どんな生活習慣を意識するといいの?
美容を意識した漢方を活用する際には、生活習慣との組み合わせも大切です。
✅ 肌のために意識したい生活習慣
✔ 毎日の食事バランスを整え、必要な栄養を意識する
✔ 夜更かしや睡眠不足を避け、規則正しい生活を心がける
✔ 適度な運動やストレッチを取り入れ、体の巡りを意識する
✔ 温かい飲み物を意識しながら、水分補給をしっかり行う
📌 ライフスタイルに取り入れやすい美容習慣
- 朝:クコの実をヨーグルトにプラスして、手軽に取り入れる
- 昼:白きくらげやナツメを使ったスープを食事に加える
- 夜:リラックスしながら、当帰芍薬散や八珍湯を取り入れる
👉 無理なく続けられる方法で、肌のコンディションを意識した美容ケアを取り入れてみましょう!
✅ 肌のコンディションを意識するなら、漢方の「巡り」「バランス」の考え方をチェック!
✅ 食事・睡眠・ストレス管理を意識することで、日々のケアに活かせる!
✅ 無理なく続けられる方法を見つけ、自分に合った美容習慣を作ろう!
👉 まずはできることから始めて、肌の巡りを意識した美容ケアを取り入れてみませんか?
肌がきれいになる漢方を取り入れるなら?おすすめの種類を紹介
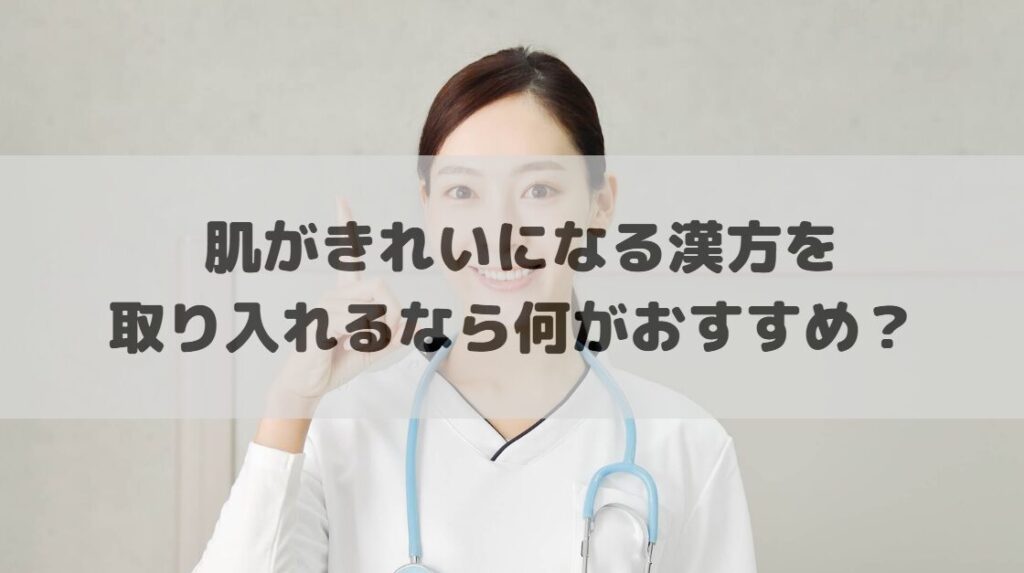
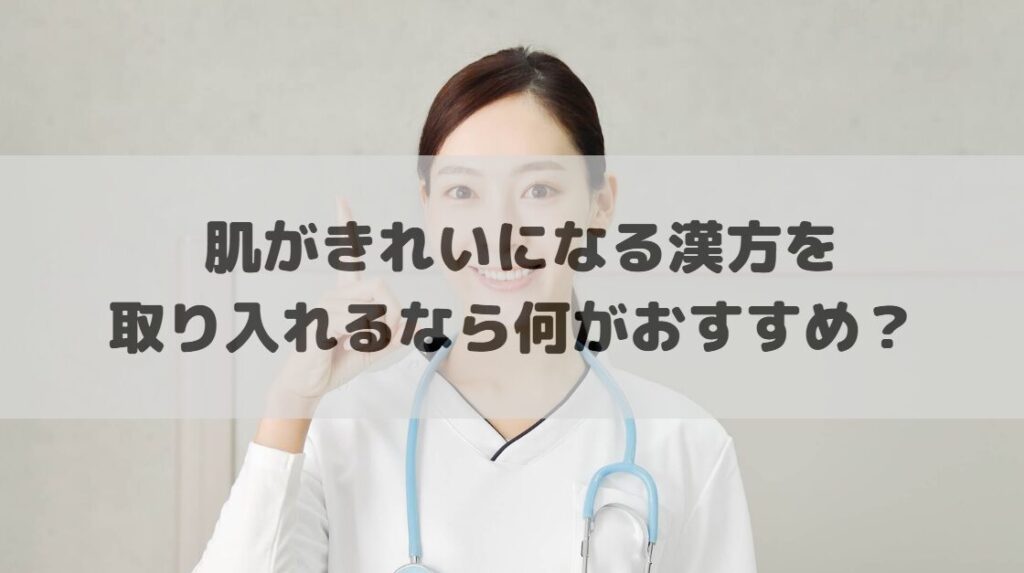



「スキンケアだけでは物足りない…」
「もっと内側からケアしたい!」
そんな方に注目されているのが、美容を意識した漢方の考え方です。
漢方の世界では、「巡り」「バランス」「すこやかさ」を大切にし、ライフスタイルに取り入れながら活用することが推奨されています。
台湾や中国では、食材としても取り入れられる漢方が多く、毎日の食事やドリンクに加えるだけで、無理なく続けられるのが魅力です。
四物湯(しもつとう)|巡りを意識しながら肌のコンディションを整える
四物湯は、漢方医学において非常に基本的な処方の一つで、「補血(ほけつ)」の代表的な漢方薬です。
つまり、血を補い、血の巡りを良くする働きがあります。→肌のコンディションを整える効果も期待!
「血」は、現代医学の血液とほぼ同じ意味ですが、漢方ではさらに、全身に栄養を与え、潤いをもたらし、精神活動を支える重要な要素と考えられています。
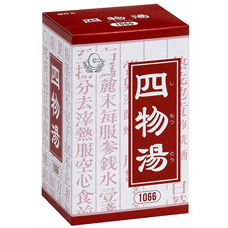
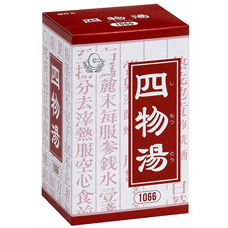
四物湯(しもつとう)
構成生薬
当帰(トウキ)、芍薬(シャクヤク)、川芎(センキュウ)、地黄(ジオウ)(通常、生地黄または熟地黄)
各生薬の一般的な薬理作用
当帰(補血、活血、調経)、芍薬(補血、止痛、筋弛緩)、川芎(活血、行気、鎮痛)、地黄(補血、滋陰、清熱) 注:四物湯としての効果効能を示すものではありません
効果効能
体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾燥、色つやの悪い体質で胃腸障害のないものの次の諸症:月経不順、月経異常、更年期障害、血の道症注、産後あるいは流産後の疲労回復、冷え症、しもやけ、しみ、手足のあれ(手足の湿疹・皮膚炎) 注血の道症:月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状
引用:ツムラ漢方四物湯エキス
適していると考えられる人(体質)
血虚(血の不足)、陰虚(体内の潤い不足、熟地黄使用時)、虚証(体力がない) (あくまで目安、要専門家診断)
副作用
まれに発疹、発赤、かゆみなどの皮膚症状、食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢などの消化器症状(頻度不明)。症状が出たら服用中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談。
四物湯(しもつとう)がおすすめな人
四物湯(しもつとう)を一言で言うと、「皮膚や髪の毛が乾燥しやすく、顔色が悪く、貧血や月経不順がある、比較的体力が低下している人」におすすめです。
- 顔色が悪く、疲れやすい女性: 特に、貧血気味で体力が低下している方。
- 皮膚や髪が乾燥している方: 血虚(血の不足)により、潤いが不足している方。
- 生理不順や生理痛がある方: 血虚や瘀血(血行不良)による月経トラブルがある方。
- 冷え性の方: 血行不良により、手足などが冷えやすい方。
- 産後の体力回復をしたい方: 出産により消耗した気血を補いたい方。
八珍湯(はっちんとう)|バランスを意識しながら、すっきりとした肌をサポート
八珍湯(はっちんとう)は、人参、白朮、茯苓、甘草、当帰、川芎、芍薬、熟地黄の8種類の生薬から構成される伝統的な漢方薬です。
主に「気血両虚(きけつりょうきょ)」と呼ばれる、体のエネルギー(気)と栄養(血)が不足した状態を改善するために用いられます。
これらの生薬が複合的に働くことで、疲労回復、消化機能の改善、血行促進、貧血改善などの効果が期待できます。
体のエネルギー(気)と栄養(血)の不足の改善に期待できるため、肌のコンディションも改善にも繋がっていきます。
八珍湯(はっちんとう)がおすすめな人
一言でいうと、「慢性的に疲れやすく、元気が出ない、体力不足を感じている人」におすすめです。
- 疲れやすく、元気がない人:なんとなく体がだるい、やる気が出ない。疲れがとれにくい、朝起きるのがつらい。
- 食欲がなく、胃腸が弱い人:食欲があまりない、食べても美味しく感じない。胃もたれしやすい、消化が悪い。
- 冷え性の人:手足が冷えやすい、寒がり。冷えからくる体の不調がある
- 貧血気味の人:めまいや立ちくらみがする。顔色が悪いと言われる
- 病後、術後で体力が落ちている人:病気や手術から回復途中で、体力をつけたい
- 月経不順がある女性:月経周期が安定しない、月経量が少ない、または過多
桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)|巡りを意識しながら、バランスの調整をサポート
桂枝茯苓丸は、漢方を代表する処方の一つで、主に「瘀血(おけつ)」と呼ばれる血行不良の状態を改善する目的で使用されます。
女性特有の症状(月経関連、更年期障害など)や、打撲などの内出血、肩こり、しみなど、幅広い症状に対して用いられることがあります。
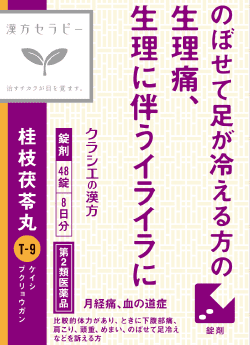
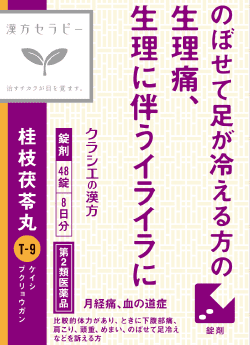
桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)
構成生薬
桂皮(ケイヒ)、茯苓(ブクリョウ)、牡丹皮(ボタンピ)、桃仁(トウニン)、芍薬(シャクヤク)
各生薬の一般的な薬理作用
桂皮(発散、温め、鎮痛)、茯苓(利水、健脾、精神安定)、牡丹皮(活血、清熱、鎮痛)、桃仁(活血、潤腸)、芍薬(補血、止痛、筋弛緩) 注:桂枝茯苓丸としての効果効能を示すものではありません
適していると考えられる人(体質)
瘀血(血の巡りが悪い状態)、実証〜中間証(比較的体力がある〜中程度)。のぼせや足の冷えを伴うことがある。(あくまで目安、要専門家診断)
効果効能
比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症:月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症注、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび 注血の道症:月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神神経症状および身体症状
引用:ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)添付文書
副作用
まれに発疹、発赤、かゆみなどの皮膚症状、食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状、肝機能障害, 腸間膜静脈硬化症(長期服用の場合)。症状が出たら服用中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談。
使い分け(参考)
・冷えが強い場合:当帰芍薬散、温経湯など
・イライラなど精神症状が強い場合: 加味逍遙散など
・便秘を伴う場合: 桃核承気湯など
(あくまでも参考)
桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)がおすすめな人
一言で言うと、「生理痛・生理不順、肩こり、シミなど、血の巡りが悪く(瘀血)、比較的体力がある人」におすすめです。
- 比較的体力があり、生理痛・生理不順が気になる女性: 生理に関するトラブルがあり、かつ、ある程度体力がある方。
- 肩こり・頭痛・めまいが気になる方: 血行不良が原因と考えられるこれらの症状がある方。
- のぼせるのに足は冷える方: 上半身は熱いが、下半身は冷えるという、いわゆる「冷えのぼせ」の症状がある方。
- シミ・くすみ・ニキビが気になる方: 血行不良が原因で肌のターンオーバーが乱れている可能性がある方。
- 打ち身(打撲)をしやすい、または治りが遅いと感じる方: 瘀血(血行不良)により、内出血が治りにくい方。
- 更年期障害の諸症状がある方: ホルモンバランスの乱れによる様々な不調がある方。
当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)|ライフスタイルを意識しながら、内側から整える
当帰芍薬散は、漢方医学において古くから用いられてきた漢方薬の一つ。
虚弱体質で、貧血傾向のある冷え症とむくみが気になる方、特に女性に適しています。
栄養を補いながら体を温め、水分代謝を促すことで、月経不順、月経痛、更年期障害、冷え性、貧血、むくみ、めまい、立ちくらみなどの症状を改善する効果が期待されますよ。
これは、これらの症状を併発している女性にとって理想的な選択肢となるでしょう。
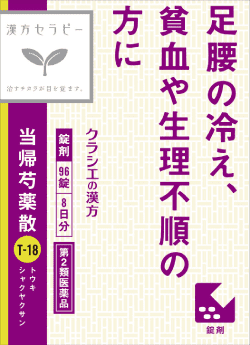
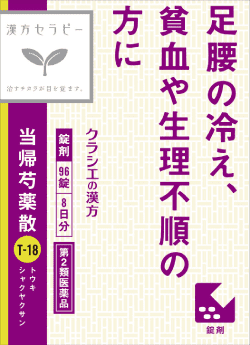
当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
構成生薬
当帰(トウキ)、芍薬(シャクヤク)、川芎(センキュウ)、茯苓(ブクリョウ)、白朮(ビャクジュツ)または蒼朮(ソウジュツ)、沢瀉(タクシャ)
各生薬の一般的な薬理作用
当帰(補血、活血、調経)、芍薬(補血、止痛、筋弛緩)、川芎(活血、行気、鎮痛)、茯苓(利水、健脾、安神)、白朮/蒼朮(健脾、利水、止汗)、沢瀉(利水、清熱) 注:当帰芍薬散としての効果効能を示すものではありません
効果・効能
体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症:月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り
引用:ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)添付文書
適していると考えられる人(体質)
血虚、瘀血、水滞、虚証。顔色が悪い、皮膚が乾燥、爪がもろい、立ちくらみ、肩こり、生理痛、しみ、くすみ、むくみ、めまい、疲れやすい、冷えやすいなど。(あくまで目安、要専門家診断
副作用
まれに発疹、発赤、かゆみなどの皮膚症状、食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢などの消化器症状(頻度不明)。症状が出たら服用中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談。
クラシエ薬品株式会社の研究によると、当帰芍薬散は、顔や手足のむくみで服用される場合、比較的効果が早く、おおよそ2週間程度から、排尿量が増えたり、むくみが軽くなったりといった改善効果があらわれると考えられています。 また、足腰の冷え症や生理不順の場合も1ヶ月程度で、症状が軽くなったり改善が見られます。
参考URL:https://www.kracie.co.jp/ph/coccoapo/magazine/18.html
当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)がおすすめな人
一言で言うと、「冷えやすく、貧血気味で、生理痛や生理不順、むくみなどがある、体力が比較的ない女性」におすすめです。
- 冷え性で疲れやすい女性: 体力があまりなく、冷えやすい方。
- 生理痛や生理不順がある方: 生理に関するトラブルを抱えている方。
- むくみやすい方: 体内の水分代謝が悪く、むくみが気になる方。
- 立ちくらみやめまいがある方: 貧血気味で、立ちくらみやめまいを起こしやすい方。
- 更年期障害の症状がある方: ホルモンバランスの乱れによる不調がある方。
- 妊娠中・産後の不調がある方: 妊娠中や産後の体力低下、貧血、むくみなどがある方。(ただし、服用は医師に相談してください)
白きくらげ・クコの実|台湾でも人気!肌がきれいになる漢方食材を活用!



「漢方をもっと手軽に取り入れたい!」
そんな方におすすめなのが、台湾でも美容を意識する方々に親しまれている「白きくらげ」と「クコの実」です。
これらの食材は、お茶やスープ、デザートに加えるだけで簡単に取り入れられるため、日々の生活に無理なく活用できるのが魅力です。
✅ 白きくらげ(銀耳/ぎんじ)とは?
台湾では、「食べる美容ドリンク」としても親しまれる食材の一つ。
白きくらげは、スープやデザートに加えやすく、無理なく食事に取り入れられます。
📌 白きくらげの取り入れ方 ✔ 白きくらげのスープ(台湾では定番の食べ方)
✔ デザートとして楽しむ(ハチミツやナツメと一緒に)
✔ 乾燥タイプを戻して、おかゆやヨーグルトにプラス
📌 台湾での活用例
- 美容を意識した「白きくらげデザート」が人気
- スープに入れることで、温かい料理としても取り入れやすい
👉 白きくらげは、料理のバリエーションが豊富で、毎日の食事に取り入れやすいのが魅力!
✅ クコの実(枸杞/くこ)とは?
「漢方といえばクコの実!」といわれるほど、古くから親しまれている食材です。
台湾では、美容を意識した食生活に取り入れやすい食材として人気があります。
📌 クコの実の取り入れ方 ✔ スープやお茶に加えて、手軽に活用!
✔ ヨーグルトやスムージーにトッピング
✔ ナツメやナッツと一緒に間食として楽しむ
📌 台湾での活用例
- 美容を意識した「クコの実茶」や「クコの実スープ」が人気
- スイーツや料理のアクセントとして活用
👉 クコの実は、お茶やスープに加えるだけで手軽に楽しめるのが魅力!
肌がきれいになる漢方を効果的に取り入れるポイントとは?
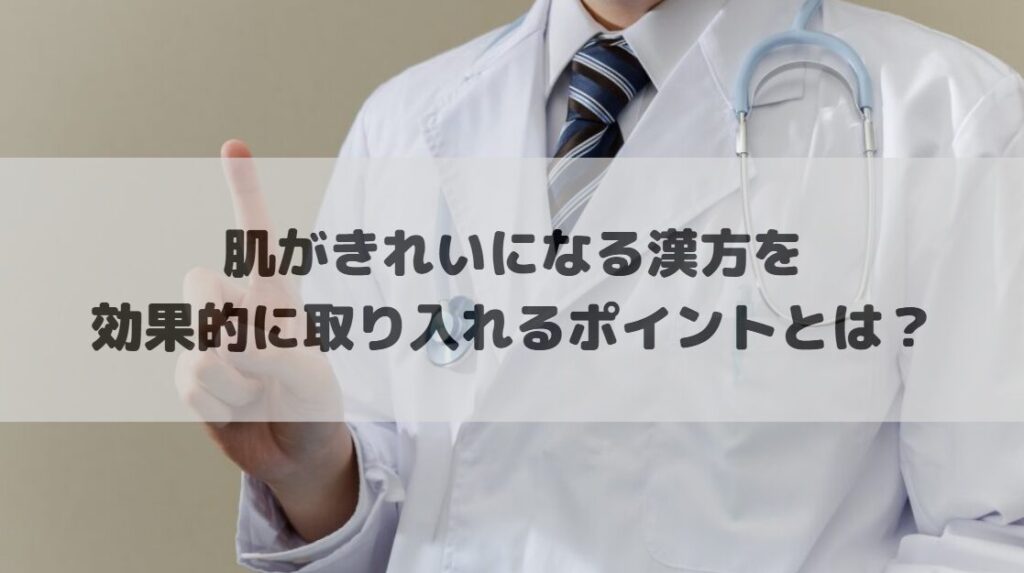
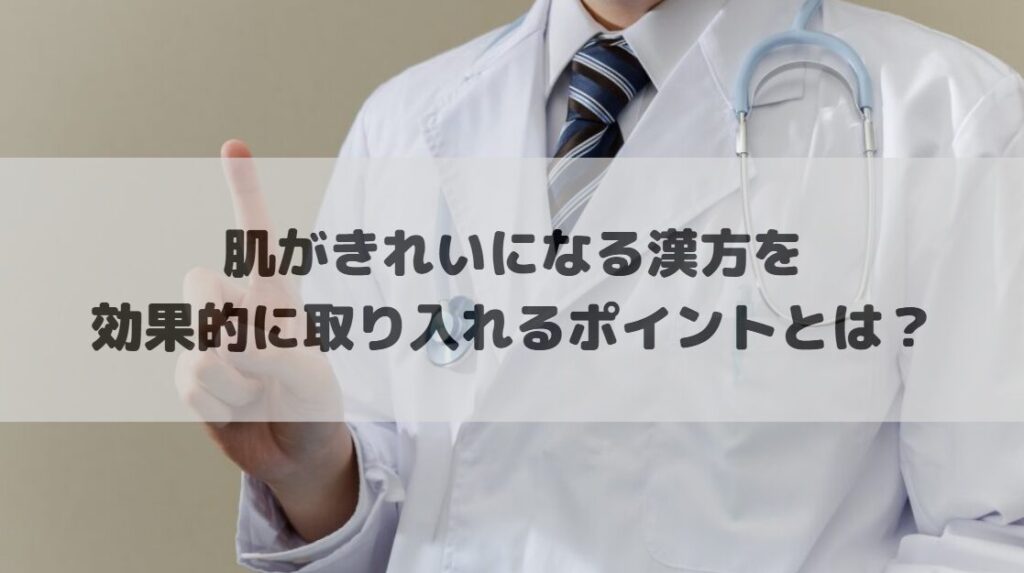



・漢方を取り入れてみたいけれど、どのように飲めばいいの?
・スキンケアや食事と一緒に活用できる?
そんな疑問を持つ方に向けて、漢方を効果的に活用するためのポイントを解説します。
漢方は「巡り」「バランス」「ライフスタイルとの組み合わせ」を意識しながら取り入れることで、日々の美容習慣のサポートに役立ちます。
それでは、まず「漢方の飲み方とタイミング」について見ていきましょう。
肌がきれいになる漢方の飲み方とタイミング|美容ケアに活かすコツ



「漢方はいつ飲めばいいの?」
美容を意識した漢方を取り入れる際は、飲むタイミングも意識すると良いでしょう。
✅ 漢方を飲むタイミングの目安
| タイミング | おすすめの漢方 | 理由 |
|---|---|---|
| 朝(起きた直後) | クコの実入り漢方茶 | 巡りを意識し、すっきりとした朝を迎えやすい |
| 食前・食後 | 四物湯・八珍湯 | 食事と一緒に取り入れやすい |
| 寝る前 | 当帰&紅花のお茶 | リラックスしながら取り入れやすい |
📌 ポイント
- 朝は「巡り」を意識した漢方を選び、すっきりとした状態をサポート
- 食事と一緒に取り入れることで、無理なく続けやすい
- 寝る前に温かい漢方茶を飲むことで、リラックスタイムの一環にできる
👉 ライフスタイルに合わせて、無理のない範囲で取り入れてみましょう!
肌がきれいになる漢方と食事の組み合わせ|相性の良い食材とは?



「食事と漢方って一緒に考えたほうがいいの?」
漢方の考え方では、食事との組み合わせを意識することで、無理なく続けやすくなると考えられています。
✅ 美容を意識したい方におすすめの食材
| 漢方成分 | 相性の良い食材 | おすすめの食べ方 |
|---|---|---|
| 四物湯(しもつとう) | クコの実・黒ゴマ | スープやお茶に加える |
| 八珍湯(はっちんとう) | 玄米・根菜類 | 煮込み料理に活用 |
| 紅花・当帰 | 生姜・ナツメ | お茶や温かいスープに入れる |
| クコの実 | ヨーグルト・ナッツ | 朝食やスムージーにトッピング |
📌 ポイント
- 冷たい食べ物や飲み物と漢方を組み合わせる場合は、温かい料理と一緒に摂るのがおすすめ
- クコの実やナツメは、スープやお茶に加えることで手軽に取り入れられる
- 漢方の風味が気になる場合は、ヨーグルトやスムージーと組み合わせると続けやすい
👉 食事との組み合わせを工夫することで、毎日の食生活に無理なく取り入れられます!
肌がきれいになる漢方とスキンケア|内外からのケアを意識した取り入れ方



「漢方はスキンケアと一緒に使えるの?」
肌の調子を整えたい方の間では、外側のケアと組み合わせることで、より意識しやすい美容習慣を作る方法が人気です。
✅ 内外からのケアを意識するポイント
✔ スキンケアと食事・漢方を組み合わせる
✔ 美容パックやフェイシャルマッサージに漢方を活用する
✔ 外側と内側からのバランスを考える
📌 おすすめの取り入れ方
- 漢方フェイシャルパック
- 材料:ハトムギ粉(小さじ1)、白芷(びゃくし)粉(小さじ1)、ヨーグルト(大さじ1)
- 使い方:
- 材料を混ぜ、ペースト状にする
- 顔全体に薄く塗り、10分ほど置く
- ぬるま湯で優しく洗い流す
- 漢方スチームケア
- 材料:ローズペタル(食用バラ)、カモミールティー、熱湯
- 使い方:
- 洗面器に熱湯を注ぐ
- ローズペタルとカモミールティーを加える
- 顔を蒸気に当てながら5~10分スチームケア
👉 スキンケアと組み合わせることで、より無理なく美容習慣を続けやすくなります!
✅ 漢方を取り入れる際は、飲み方やタイミングを意識することが大切!
✅ 食事との組み合わせを工夫することで、無理なく続けられる!
✅ スキンケアと組み合わせ、外側と内側の両方からアプローチするのもおすすめ!
肌がきれいになる漢方を試す際の注意点と正しい活用法





「肌のコンディションを意識して漢方を取り入れたいけれど、どれを選べばいいの?」
「漢方だけでなく、日々の習慣も見直したほうがいい?」
そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
漢方は「巡り」「バランス」「継続」を意識しながら活用することが大切です。
また、食事・運動・睡眠のバランスと組み合わせることで、無理なく続けやすくなるという考え方があります。
まずは、自分に合った漢方の選び方からチェックしていきましょう。
自分に合った肌がきれいになる漢方の選び方|体質やライフスタイルに合わせた活用法



「漢方にはいろいろな種類があるけれど、どれを選べばいいの?」
自分に合った漢方を選ぶには、体質やライフスタイルに合わせることが大切です。
✅ 体質・ライフスタイル別のおすすめ美容漢方
| タイプ | 特徴 | おすすめの漢方 |
|---|---|---|
| 巡りを意識したい | すっきりとしたコンディションを目指す | 四物湯(しもつとう) |
| バランスを整えたい | 体の調和を意識したい | 八珍湯(はっちんとう) |
| すこやかな毎日を意識したい | 日々のリズムを意識したい | 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん) |
| 美容習慣として気軽に取り入れたい | 食事と一緒に摂りやすい | クコの実・白きくらげ |
📌 ポイント
- 自分の目的やライフスタイルに合ったものを選ぶと、無理なく続けやすい!
- 手軽に試したい場合は、美容漢方茶や漢方スープから取り入れるのもおすすめ!
👉 まずは自分の体質やライフスタイルに合った漢方を見つけ、無理なく始めてみましょう!
肌がきれいになる漢方だけに頼らない!食生活・運動・睡眠のバランスを意識しよう



「漢方を取り入れているのに、肌の調子が安定しない…」
そんなときは、食生活や運動・睡眠などの生活習慣を見直すことが大切です。
✅ 美容を意識するために重要な3つのポイント
✔ 食生活 → 栄養バランスを意識し、食事からも巡りを整える
✔ 運動習慣 → 軽いストレッチやウォーキングで巡りを意識する
✔ 睡眠リズム → 規則正しい生活を意識し、無理のないリズムを作る
📌 おすすめの習慣
- 食事:クコの実やナツメ、白きくらげを活用し、無理なく栄養バランスを整える
- 運動:ヨガや軽いストレッチで巡りを意識する
- 睡眠:寝る前のスマホ時間を短縮し、リラックスできる環境を作る
👉 漢方だけでなく、日常生活の習慣を意識することで、より続けやすい美容習慣を作ることができます!
肌がきれいになる漢方を日常のケアと組み合わせて、継続しやすい習慣にする



「せっかく漢方を取り入れるなら、長く続けられる方法を知りたい!」
漢方は継続することが大切とされているため、無理のない範囲で習慣にすることがポイントです。
✅ 継続しやすい漢方の取り入れ方
✔ 毎日続けられる方法を選ぶ(お茶・スープなど)
✔ スキンケアや食事と組み合わせることで無理なく続ける
✔ 生活習慣と組み合わせ、トータルで意識する
📌 おすすめの続け方
- 朝:クコの実をヨーグルトにプラスして、手軽に取り入れる
- 昼:白きくらげやナツメを使ったスープを食事に加える
- 夜:リラックスしながら、紅花茶や当帰芍薬散を取り入れる
👉 無理なく続けられる方法を見つけて、自分に合った美容習慣を作っていきましょう!
✅ 自分の体質やライフスタイルに合った漢方を選ぶことが大切!
✅ 漢方だけに頼らず、食事・運動・睡眠のバランスも意識することが重要!
✅ スキンケアや食生活と組み合わせて、無理なく続けられる習慣を作る!
参考文献
公的機関・専門機関のウェブサイト:
厚生労働省:eJIM(日本統合医療学会)https://www.ejim.ncgg.go.jp/public/herbs/index.html
国立健康・栄養研究所:「健康食品」の安全性・有効性情報 https://hfnet.nibiohn.go.jp/
日本漢方生薬製剤協会
日本産婦人科学会、日本産科婦人科内視鏡学会、日本女性医学学会(旧日本更年期医学会):https://www.jsog.or.jp/
学術論文データベース:
PubMed:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
Google Scholar: https://scholar.google.co.jp/
書籍:
漢方に関する書籍
- 例:「漢方医学」, 「和漢薬の事典」, 「漢方薬・生薬活用QA」など
免責事項
本記事は、漢方やメンタルケアに関する一般的な情報を提供するもので、医師の診断・治療に取って代わるものではありません。個々の症状や体質には個人差があり、必ずしも同じ効果が得られるとは限りません。体調に異変を感じた場合は自己判断せず、速やかに医療機関にご相談ください