
・最近、集中できない
・物忘れが増えた…
それ、脳のSOSサインかも!? 年齢やストレス、生活習慣で脳は意外とダメージを受けています。
でも大丈夫!この記事では、脳の働きが低下する原因を徹底解説し、さらに脳を活性化するメカニズムを解明。
あなたに合った漢方の選び方、今日からできる生活習慣改善まで、具体的な方法を伝授します。
さあ、漢方のチカラと生活習慣で、クリアな思考と冴えわたる毎日を取り戻しましょう!



KANKAN専属アドバイザーのルナです。
漢方に精通した知見を惜しみなく皆さんにお伝えしていきますね!
なぜ?脳が活性化しない原因を徹底解剖!漢方的視点もプラス
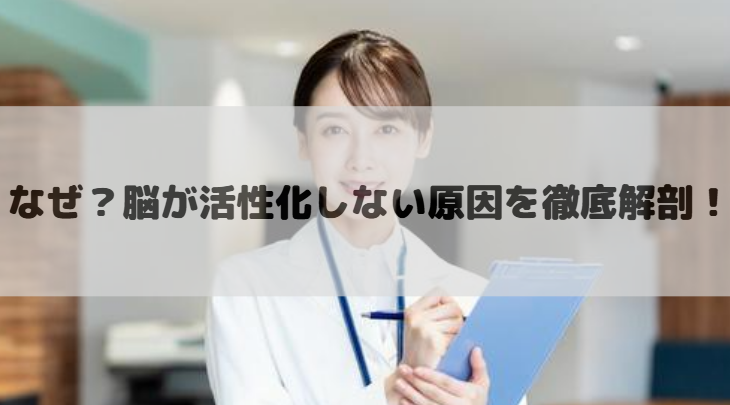
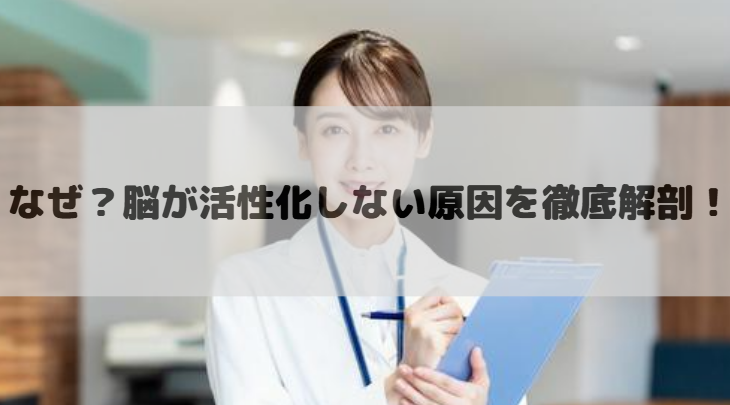



最近、集中力が続かないし、物忘れもひどい…。これって歳のせい?何が原因で、どうすれば脳は活性化するの?
「集中力」「記憶力」「思考力」…これらの脳の働きは、私たちの日常生活や仕事のパフォーマンスに大きく影響します。
しかし、年齢を重ねるにつれて、あるいは日々の生活習慣によって、脳の働きが低下してしまうことがあります。
「最近、なんだか頭がスッキリしない…」と感じている方もいるかもしれません。
この章では、脳が活性化しない原因を、西洋医学と漢方医学の両面から詳しく解説していきます。
現代人に多い?脳の働きが低下する5つの要因



仕事も忙しいし、ストレスも多い…。生活習慣が脳の働きに影響するって本当?
私たちの脳は、非常にデリケートな臓器であり、様々な要因によってその働きが左右されます。
ここでは、現代人に特に多い、脳の働きを低下させる5つの要因について見ていきましょう。
- 加齢による脳の変化:
- 神経細胞の減少: 年齢とともに、脳の神経細胞(ニューロン)の数が減少することが知られています。
- 脳血流の低下: 加齢により、脳への血流が低下し、酸素や栄養の供給が不足しがちになります。
- 神経伝達物質の変化: ドーパミンやセロトニンなど、脳の働きに重要な神経伝達物質の量が減少することがあります。
- 慢性的なストレスと脳への悪影響:
- コルチゾールの過剰分泌: ストレスが続くと、副腎からコルチゾールというホルモンが過剰に分泌されます。コルチゾールは、海馬(記憶を司る部位)を萎縮させ、記憶力や学習能力を低下させる可能性があります。
- 神経伝達物質のバランスの乱れ: ストレスは、セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質のバランスを崩し、うつ病や不安障害などの精神疾患の原因となることもあります。
- 睡眠不足が脳に与えるダメージ:
- 老廃物の蓄積: 睡眠中に、脳は日中の活動で生じた老廃物を排出します。睡眠不足は、この老廃物の排出を妨げ、脳の働きを低下させます。
- 記憶の定着阻害: 睡眠は、記憶の定着に重要な役割を果たします。睡眠不足は、記憶の定着を妨げ、学習効果を低下させます。
- 神経細胞の修復:睡眠中に行われる
- 偏った食生活と脳の栄養不足:
- 糖質過多: 糖質の過剰摂取は、血糖値の急上昇・急降下を招き、脳のエネルギー供給を不安定にします。
- ビタミン・ミネラル不足: ビタミンB群、ビタミンD、亜鉛、鉄などのビタミン・ミネラルは、脳の働きに不可欠です。これらの栄養素が不足すると、脳の機能が低下する可能性があります。
- 必須脂肪酸不足: DHAやEPAなどの必須脂肪酸は、脳の細胞膜の構成成分であり、脳の働きに重要です。
- 運動不足による脳への影響:
- 脳血流の低下: 運動不足は、全身の血流を悪化させ、脳への血流も低下させます。
- 神経伝達物質の減少: 運動は、ドーパミンやセロトニンなどの神経伝達物質の分泌を促進します。運動不足は、これらの神経伝達物質の減少につながる可能性があります。
- 海馬の萎縮: 運動不足は、海馬の萎縮を招き、記憶力や学習能力を低下させる可能性があります。
漢方医学ではこう考える!脳の不調は「気・血・水」の乱れ



漢方では、脳の働きをどう考えるの?体質と関係があるの?
漢方医学では、脳の働きは、「気(き)・血(けつ)・水(すい)」という3つの要素のバランスによって支えられていると考えます。
これらの要素のいずれかが不足したり、滞ったりすると、脳の働きが低下し、様々な不調が現れると考えられています。
- 「気」の不足・滞り:
- 気虚(ききょ): エネルギー不足の状態。
- 症状: 倦怠感、疲労感、意欲低下、集中力低下、記憶力低下など。
- 気滞(きたい): 気の流れが滞った状態。
- 症状: イライラ、不安感、抑うつ感、頭重感、頭痛など。
- 気虚(ききょ): エネルギー不足の状態。
- 「血」の不足・滞り(瘀血):
- 血虚(けっきょ): 血液が不足した状態。
- 症状: めまい、立ちくらみ、顔色が悪い、記憶力低下、不眠など。
- 瘀血(おけつ): 血液の流れが滞った状態。
- 症状: 頭痛、肩こり、物忘れ、集中力低下、思考力低下など。
- 血虚(けっきょ): 血液が不足した状態。
- 「水」の滞り(痰湿):
- 痰湿(たんしつ): 体内の余分な水分や老廃物が溜まった状態。
- 症状: 頭重感、めまい、思考力低下、集中力低下、記憶力低下など。
- 痰湿(たんしつ): 体内の余分な水分や老廃物が溜まった状態。
- 「腎」の機能低下: * 腎虚(じんきょ):生命エネルギーの根本である「腎」が弱った状態 * 症状: 加齢による脳機能低下、記憶力低下、足腰の弱り、など
【まとめ】
この章では、脳が活性化しない原因について、西洋医学的な視点と漢方医学的な視点の両方から解説しました。次の章では、脳が活性化するメカニズムについて、さらに詳しく見ていきましょう。
脳が活性化するメカニズムとは?カギは神経伝達物質と血流!
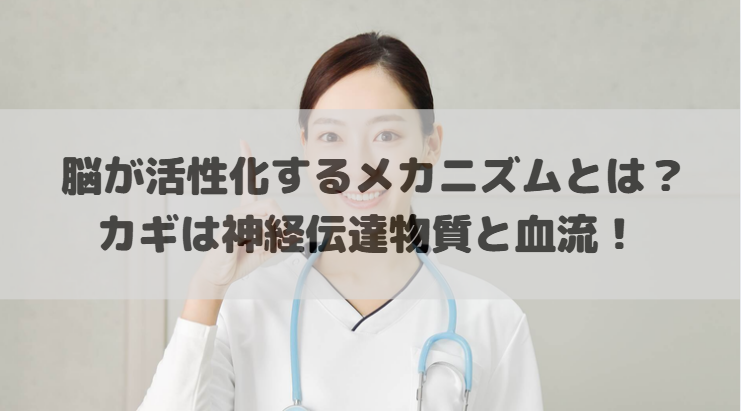
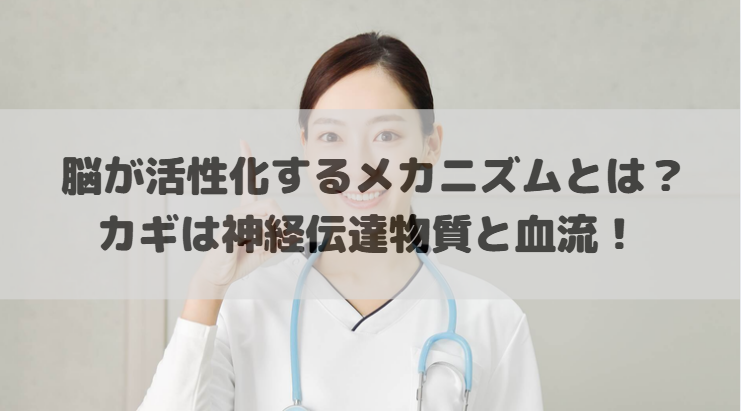



脳が活性化するって、具体的にどういうこと?
神経伝達物質とか血流とか、難しそうだけど、私にも関係あるの?
「集中して仕事に取り組みたい」「いつまでも記憶力を保ちたい」…そう願うなら、まずは脳が活性化するメカニズムを知ることが大切です。
この章では、脳の活性化に欠かせない「神経伝達物質」と「血流」、そして「脳の可塑性」について、分かりやすく解説していきます。
脳の活性化に重要な「神経伝達物質」の働き



神経伝達物質って、よく聞くけど、一体何?」「私の脳の働きと、どう関係があるの?
神経伝達物質とは、脳内の神経細胞(ニューロン)の間で情報を伝達する役割を担う化学物質です。
神経細胞は、電気信号と化学物質を使って情報をやり取りしており、神経伝達物質は、この化学物質による情報伝達の主役です。
- 神経伝達物質の働き:
- 思考、記憶、学習、感情、意欲、運動など、脳のあらゆる機能に関与
- 100種類以上存在し、それぞれ異なる役割を持つ
- 特定の神経伝達物質が不足したり、過剰になったりすると、脳の機能に様々な影響が出る
【主要な神経伝達物質の種類と役割】
| 神経伝達物質 | 主な役割 | 不足すると… | 過剰になると… |
| ドーパミン | 意欲、快感、学習、運動調節 | 意欲低下、無気力、集中力低下、パーキンソン病 | 幻覚、妄想、統合失調症 |
| セロトニン | 精神安定、睡眠、食欲調節 | うつ病、不安障害、不眠、過食 | セロトニン症候群(興奮、発汗、振戦など) |
| ノルアドレナリン | 覚醒、集中力、注意、ストレス反応 | 注意力散漫、無気力、うつ病 | 不安、焦燥感、高血圧 |
| アセチルコリン | 記憶、学習、認知機能、筋肉の収縮 | アルツハイマー病、記憶力低下、学習能力低下 | 吐き気、嘔吐、下痢、筋力低下 |
| GABA | リラックス、抑制、不安軽減 | 不安、緊張、けいれん、てんかん | 過度の眠気、意識レベルの低下 |
【神経伝達物質のバランスの重要性】
これらの神経伝達物質は、それぞれが単独で働くのではなく、互いに影響し合いながら、複雑なネットワークを形成しています。
脳の機能を正常に保つためには、これらの神経伝達物質のバランスがとれていることが非常に重要です。
脳の活性化には「血流」が不可欠!



脳の血流って、そんなに大事なの?」「血流を良くするにはどうすればいいの?
脳は、体重の約2%程度の重さしかないにもかかわらず、全身の酸素消費量の約20%を消費する、非常にエネルギーを必要とする臓器です。
脳の神経細胞は、酸素と栄養(主にブドウ糖)を血液から供給されて活動しています。そのため、脳への血流が滞ると、脳の機能が低下してしまいます。
- 脳血流と脳機能の関係:
- 脳血流は、脳の神経細胞に酸素と栄養を供給する
- 脳血流が低下すると、神経細胞の活動が低下し、集中力、記憶力、思考力などが低下する
- 慢性的な脳血流の低下は、認知症のリスクを高める可能性もある
【脳血流を改善する方法】
- 運動:
- 有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳など)は、全身の血流を促進し、脳血流も増加させる
- 軽い筋力トレーニングも、血流改善に効果的
- 食事:
- DHA・EPA: 青魚に多く含まれるDHA・EPAは、血液をサラサラにし、脳血流を改善する効果が期待できる
- 抗酸化物質: ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノールなどは、活性酸素を除去し、血管を保護する
- バランスの取れた食事: 糖質、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂取する
- 睡眠:
- 質の良い睡眠は、脳の老廃物を排出し、脳血流を改善する
- ストレス管理:
- ストレスは、血管を収縮させ、脳血流を低下させる
- リラックスできる時間を持ち、ストレスを溜めないようにする
- 漢方: * 一部の漢方には血流を改善する効果があるとされているものも。
- その他:
- 禁煙、節酒
- 十分な水分補給
脳の可塑性と活性化



脳の可塑性って何?」「脳は、いくつになっても成長するの?
脳の可塑性とは、学習や経験によって、脳の構造や機能が変化する能力のことです。
新しいことを学んだり、新しい経験をしたりすると、脳内の神経回路が強化されたり、新しい神経回路が形成されたりします。
- 脳の可塑性と活性化:
- 脳の可塑性は、年齢に関係なく存在する
- 新しいことに挑戦したり、積極的に学習したりすることで、脳の可塑性を高め、脳を活性化することができる
- 脳トレ(読書、計算、パズル、ゲームなど)は、脳の可塑性を高めるのに有効
【まとめ】
この章では、脳が活性化するメカニズムについて、神経伝達物質、血流、脳の可塑性という3つの観点から解説しました。次の章では、これらのメカニズムを踏まえ、脳の活性化をサポートする漢方薬について詳しくご紹介します。
【目的別】脳の活性化をサポートする漢方5選|選び方のポイント





「脳の活性化に良い漢方って、具体的にどんなものがあるの?」「私に合う漢方を選ぶには、どうすればいいの?」
前の章では、脳が活性化するメカニズムについて解説しました。この章では、いよいよ、あなたの目的や体質に合わせた漢方薬の選び方と、具体的な漢方薬の種類についてご紹介します。
漢方薬は、体の内側から働きかけ、脳の機能改善をサポートします。
ぜひ、あなたにぴったりの漢方薬を見つけて、クリアな思考と冴えわたる毎日を取り戻しましょう。
集中力・記憶力UP↑におすすめの漢方



「仕事や勉強に集中できない…」「最近、物忘れが多くて…」
そんな悩みを抱えている方におすすめの漢方をご紹介!
漢方では、集中力や記憶力の低下は、「気」の不足や「血」の不足・滞りなどが原因と考えます。
これらのバランスを整えることで、脳の働きを高め、集中力・記憶力UPをサポートします。
- 補中益気湯(ほちゅうえっきとう):
- 期待できる効果: 疲労倦怠感、食欲不振、気力低下などを改善し、心身を元気づけることで、集中力・記憶力UPをサポートします。「気」を補い、消化機能を高める働きがあります。
- 向いているタイプ: 疲れやすい、食欲がない、胃腸が弱い、気力がない方。
- 注意点: 体力が充実している方、のぼせやほてりがある方には、向かない場合があります。
- 帰脾湯(きひとう):
- 期待できる効果: 不眠、精神不安、貧血などを改善し、記憶力や集中力を高める効果が期待できます。「気」と「血」を補い、精神を安定させる働きがあります。
- 向いているタイプ: 疲れやすい、貧血気味、不眠、不安感がある方。
- 注意点: 胃腸が弱い方は、服用に注意が必要です。
- 酸棗仁湯(さんそうにんとう):
- 期待できる効果: 不眠、精神不安などを改善し、心身をリラックスさせることで、集中力UPをサポートします。「心(しん)」の機能を整え、精神を安定させる働きがあります。
- 向いているタイプ: ストレスが多い、不眠、神経過敏な方。
- 注意点: 下痢や軟便になりやすい方は、服用に注意が必要です。
その他:人参養栄湯(にんじんようえいとう)、加味帰脾湯(かみきひとう)など。
ストレス緩和・リラックスにおすすめの漢方



「ストレスで頭がパンクしそう…」「リラックスして、脳を休ませたい…」そんな悩みを抱えている方におすすめの漢方をご紹介!
漢方では、ストレスは「気」の滞りを引き起こし、脳の働きを低下させると考えます。
気の流れをスムーズにし、心身をリラックスさせることで、脳の活性化をサポートします。
- 加味逍遙散(かみしょうようさん):
- 期待できる効果: イライラ、不安感、不眠、更年期障害などの症状を改善し、精神を安定させることで、ストレスを緩和します。気の流れを良くし、「血」の巡りも改善します。
- 向いているタイプ: イライラしやすい、怒りっぽい、生理前に不調がある女性。
- 注意点: 体力が低下している方、胃腸が弱い方は、服用に注意が必要です。
- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう):
- 期待できる効果: ストレスによる神経過敏、不眠、動悸などを改善し、精神を安定させることで、ストレスを緩和します。「肝」の機能を整え、気の流れをスムーズにします。
- 向いているタイプ: ストレスが多い、神経質、動悸、不眠がある方。
- 注意点: 体力が低下している方、胃腸が弱い方は、服用に注意が必要です。
- 抑肝散(よくかんさん):
- 期待できる効果: 神経の高ぶりを鎮め、イライラ、不眠、神経症などを改善することで、ストレスを緩和します。「肝」の機能を整え、気の流れをスムーズにします。
- 向いているタイプ: イライラしやすい、怒りっぽい、神経過敏な方、お子さんの夜泣きなど。
- 注意点: 体力が低下している方、胃腸が弱い方は、服用に注意が必要です。
その他:半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)、桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)など
脳の血流改善におすすめの漢方



「脳の血流を良くして、スッキリしたい!」「血流改善に効果的な漢方ってあるの?」
漢方では、脳の血流不足は「血」の滞り(瘀血)が原因と考えます。
血流を改善することで、脳に十分な酸素と栄養を届け、脳の活性化をサポートします。
- 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん):
- 期待できる効果: 血行を促進し、ホルモンバランスの乱れによる諸症状(のぼせ、足の冷え、生理痛、生理不順、肩こりなど)を改善します。
- 向いているタイプ: 血行不良、冷えのぼせ、生理痛、生理不順、肩こりなどがある方。
- 注意点: 妊娠中の方、出血傾向のある方は、服用に注意が必要です。
- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん):
- 期待できる効果: 血行を促進し、冷え性、貧血、生理痛、生理不順、更年期障害などを改善します。
- 向いているタイプ: 冷え性、貧血気味、生理痛、生理不順、むくみやすい方。
- 注意点: 胃腸が弱い方は、服用に注意が必要です。
その他: 芎帰調血飲第一加減(きゅうきちょうけついんだいいちかげん)、通導散(つうどうさん)など
漢方薬を選ぶ上での注意点



「漢方薬を選ぶときに、気をつけることは?」「専門家への相談は必要?」
漢方薬は、自分の体質や症状に合ったものを選ぶことが大切です。ここでは、漢方薬を選ぶ上での注意点をご紹介します。
- 専門家(医師、薬剤師、登録販売者)への相談の重要性:
- 漢方薬は、同じ症状でも、体質によって合うものが異なります。
- 自己判断で選ぶのではなく、必ず専門家に相談し、適切な漢方薬を選んでもらいましょう。
- 特に、持病がある方、他の薬を服用している方、妊娠中・授乳中の方は、必ず事前に相談してください。
- 体質との相性:
- 漢方薬には、それぞれ「証(しょう)」(体質や症状を総合的に判断したもの)があります。
- 自分の「証」に合った漢方薬を選ぶことが、効果を得るための重要なポイントです。
- 副作用:
- 漢方薬は、一般的に副作用が少ないとされていますが、体質や症状によっては、まれに副作用が出ることがあります。
- 服用中に気になる症状が現れた場合は、すぐに服用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。
- 他の薬との飲み合わせ:
- 他の薬と漢方薬を併用する場合は、必ず医師や薬剤師に相談してください。
- 飲み合わせによっては、薬の効果が弱まったり、強まったり、副作用が出やすくなったりする可能性があります。
【まとめ】
この章では、目的別に脳の活性化をサポートする漢方薬と、漢方を選ぶ上での注意点をご紹介しました。漢方薬は、体質や症状に合わせて、専門家と相談しながら、適切に活用することが重要です。








