
二日酔いがひどすぎて、もう何を試しても効かない…どうにかしてスッキリしたい!
そんな悩みを抱えるあなたに試してほしいのが、漢方薬『五苓散』。
二日酔いの症状に特化した成分が含まれており、体調を早く回復させてくれる可能性があります。
この記事では『五苓散』の効果的な使い方から、市販商品までしっかりご紹介。
早速、二日酔いを解消したい方にぴったりな情報をお届けします!



KANKAN専属アドバイザーのルナです。
漢方に精通した知見を惜しみなく皆さんにお伝えしていきますね!
二日酔いに効く!漢方『五苓散』の効果とは?
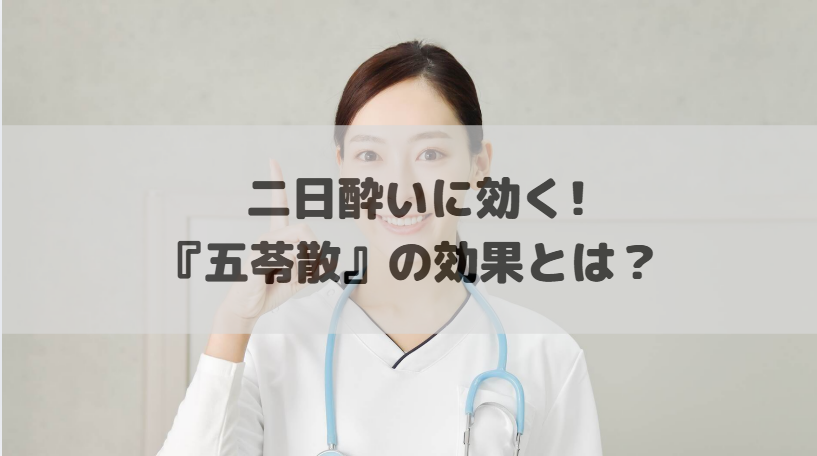
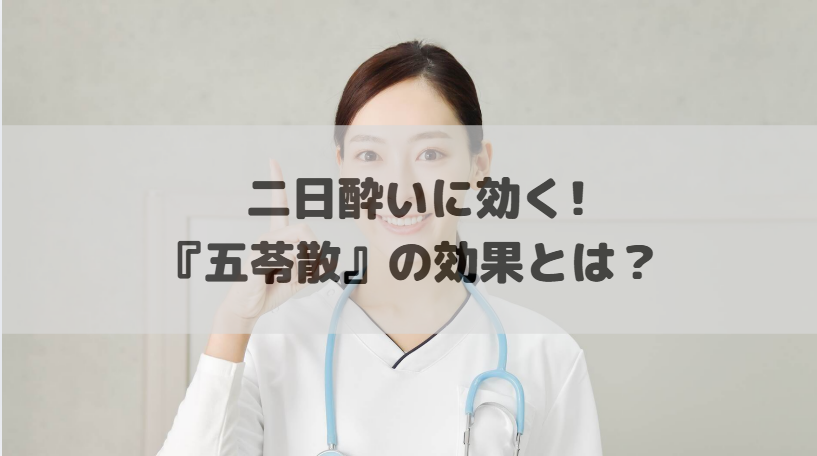



「お酒を飲んだ翌朝、顔がパンパンにむくんでる…」
「頭が痛くて、胃もムカムカする…」
そんな二日酔いの不快な症状を和らげる漢方薬が『五苓散(ごれいさん)』です。
五苓散は、体内の水分バランスを整え、余分な水分を排出することで、むくみ・頭痛・吐き気を改善する漢方薬として知られています。
ここでは、五苓散がなぜ二日酔いに効くのか?基本成分とその働きについて詳しく解説します!
『五苓散』が二日酔いに効く理由とそのメカニズム



五苓散ってどうして二日酔いに効くの?
その理由は、五苓散が「体内の水分バランスを調整する力」に優れているからです。
✅ 二日酔いの主な原因
二日酔いの症状(むくみ・頭痛・吐き気・倦怠感)は、主に以下の2つが原因です。
1. アルコールの利尿作用による脱水
- 飲酒によって水分が大量に排出される
- 体内の水分が足りなくなり、血液がドロドロに → 頭痛・倦怠感が発生!
2. 体内に余分な水分が滞留する「水滞」
- アルコールの影響で水分バランスが乱れる
- 体に水が溜まり、むくみ・吐き気・めまいが発生!
五苓散は、この「脱水」と「水滞」の両方を調整するため、二日酔いの改善に非常に効果的です。
✅ 五苓散の作用メカニズム
| 五苓散の効果 | 二日酔いの症状への働き |
|---|---|
| 体内の水分バランスを整える | 余分な水分を排出し、むくみを軽減 |
| 胃腸の機能をサポート | 吐き気・胃もたれを和らげる |
| 腎機能を助け、利尿を促進 | アルコールによる脱水を防ぐ |
| 血流をスムーズにする | 頭痛・倦怠感を軽減し、スッキリ回復! |
📌 ポイント
- 「脱水しすぎず、水を溜めすぎない」バランスを取るのが五苓散の最大の特徴!
- 二日酔いだけでなく、むくみや水分代謝の乱れが気になる人にも効果的!
👉 「五苓散=体の水分バランスを調整する漢方」だからこそ、二日酔いにピッタリ!
『五苓散』の基本的な成分と作用
五苓散は、5つの生薬から構成されており、それぞれが体内の水分代謝を改善し、二日酔いの症状を和らげる働きを持っています。
✅ 五苓散の基本成分と作用
| 成分(生薬) | 主な作用 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 沢瀉(たくしゃ) | 利尿作用 | 余分な水分を排出し、むくみを軽減 |
| 茯苓(ぶくりょう) | 水分バランス調整 | 胃腸の水分調整を助け、吐き気を防ぐ |
| 猪苓(ちょれい) | 排尿促進 | 体内の水分を適切に循環させる |
| 桂皮(けいひ) | 体を温め、血流促進 | 血流を良くし、頭痛・倦怠感を緩和 |
| 白朮(びゃくじゅつ) | 胃腸を強化 | 胃腸の働きをサポートし、消化不良を防ぐ |
📌 ポイント
- 五苓散の最大の特徴は、「排出」と「補う」のバランスが取れていること!
- 余分な水分を排出しながら、必要な水分を保持することで、二日酔いの回復をスムーズにする!
👉 「むくみ・頭痛・吐き気」の三重苦を解消する、生薬の組み合わせが絶妙!
✅ 五苓散は「水分バランス」を調整し、二日酔いのむくみ・頭痛・吐き気を改善!
✅ 脱水しすぎず、余分な水分を排出する絶妙なバランスが二日酔いに最適!
✅ 5つの生薬が相互に作用し、腎機能・胃腸・血流を整えてスムーズな回復をサポート!
二日酔いを早く解消するための漢方『五苓散』の使い方
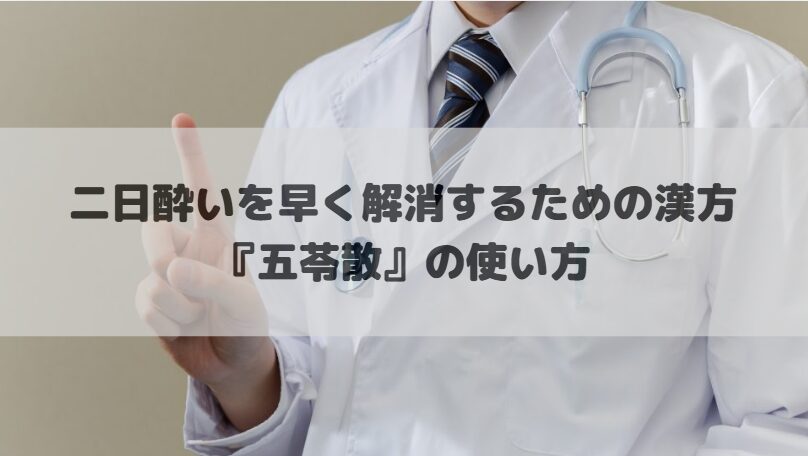
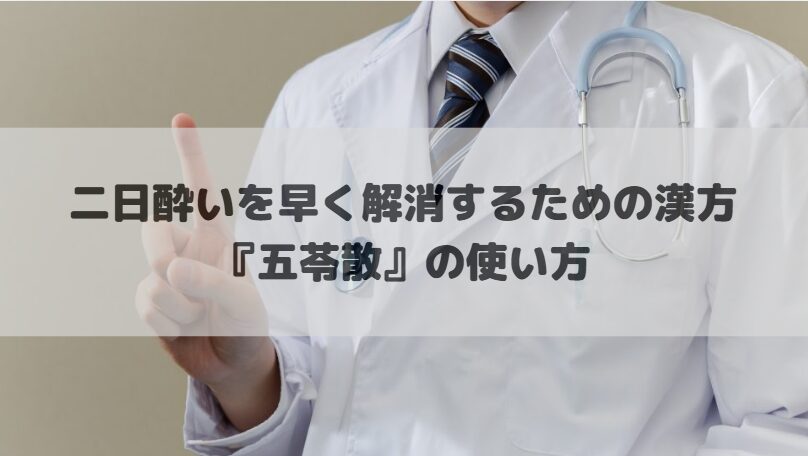



二日酔い、もう何とかしたい!でもどう使うのが一番効果的?
二日酔いを早く解消するために、「五苓散」が有効だと聞いたけど、どうやって使うのがベストなのか、悩んでいませんか?
『五苓散』は、むくみや吐き気、頭痛を緩和し、二日酔いの回復を早める漢方薬です。
効果を最大限に引き出すためには、服用のタイミングや飲み方に工夫が必要です。ここではその最適な使い方をご紹介します。
- 飲み会前に服用:肝臓の負担を軽減し、アルコールの代謝を助けるため、飲み過ぎを防ぐ。
- 飲み会後に服用:アルコールの分解を早め、二日酔いの症状を和らげる。
- 一回分の服用量を守る:過剰摂取を避け、体に優しい方法で効率よく効果を発揮。
- 水分と一緒に摂取:体内での吸収を助けるため、必ず水分と一緒に服用。
『五苓散』の服用タイミングを上手に活用することで、二日酔いを早く解消する手助けになります。
飲み会前後における『五苓散』の最適な服用タイミング



飲み会前に飲んでも効果があるの?飲み過ぎてからじゃ遅いのかな?
飲み会前後に『五苓散』を使う際、最適なタイミングが重要です。アルコールが体内でどのように作用するかを理解したうえで服用タイミングを調整することで、効果を最大化できます。
- 飲み会前に服用:予防として、肝臓の負担を軽減。二日酔いになる前に体を整える。
- 飲み会後に服用:アルコールを分解し、二日酔いの症状(吐き気、頭痛、むくみ)を和らげる。
- タイミングの目安:飲み会の開始30分前と、終わった直後に服用するのが理想。
これらのタイミングで服用することで、二日酔いの症状を軽減し、翌朝スッキリ目覚めることができます。
『五苓散』の効果を最大化する飲み方と生活習慣



『五苓散』を飲んだ後、何か気をつけるべきことはある?生活習慣が影響するって本当?
『五苓散』を効果的に使うためには、飲み方だけでなく、生活習慣を見直すことも大切です。
ちょっとした工夫で、より早く、確実に二日酔いから回復できます。
- 飲み方のポイント
- 食後に飲む:胃腸に優しく、吸収がスムーズに。
- 水分を多めに摂取:『五苓散』を飲む際に水分をしっかりと補給することで、効果が発揮されやすい。
- 生活習慣の改善
- 十分な睡眠:睡眠はアルコールの分解を助け、体の回復を促進します。
- 軽い運動:血行を良くすることで、体内の毒素を排出しやすくします。
- 栄養バランスの取れた食事:肝臓に負担をかけないよう、消化の良い食事を心がけましょう。
『五苓散』の効果を最大化するためには、これらの飲み方や生活習慣を意識することで、二日酔いからの回復が早まります。
漢方『五苓散』の商品紹介|市販で買えるおすすめ商品
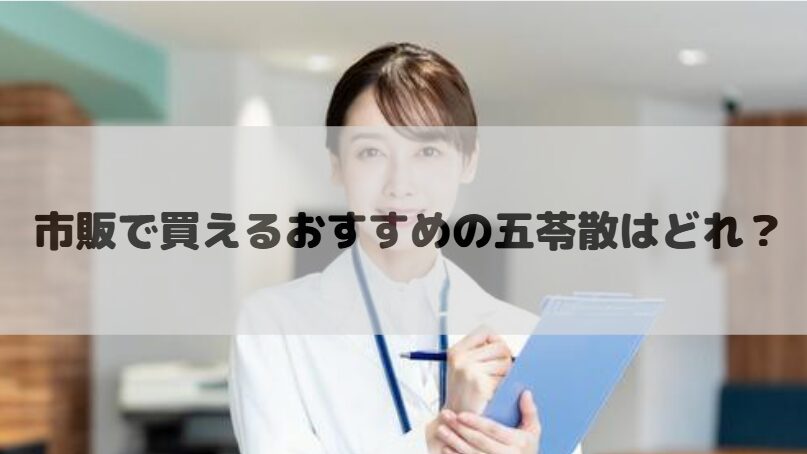
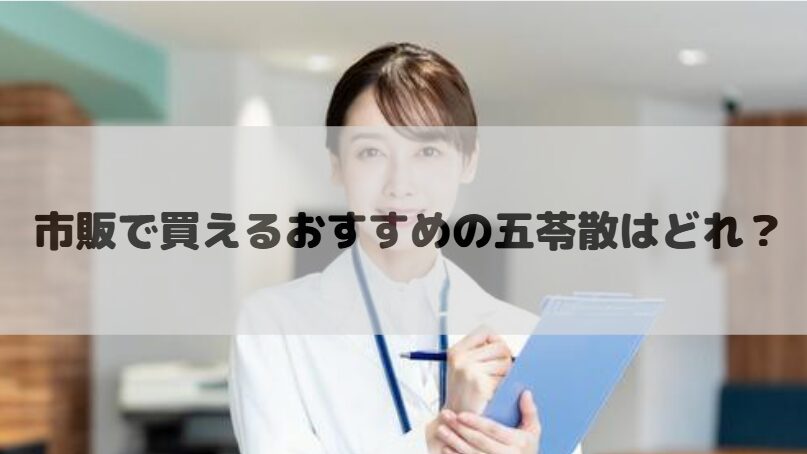



どの五苓散を選べばいいの?数多くの市販薬の中から、どれが一番効果的?
『五苓散』は二日酔いを解消するために人気のある漢方薬ですが、さまざまな商品が市販されています。自分にぴったりの一品を選ぶことが重要です。
本章では、あなたの二日酔い解消をサポートするおすすめの『五苓散』商品を紹介します。
効果的に使うためのポイントも合わせて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
二日酔い解消におすすめの市販『五苓散』商品



飲み過ぎて二日酔いがひどい…。市販の五苓散で早く治したい!
市販されている『五苓散』商品はそれぞれ特徴が異なります。ここでは二日酔いを解消するための最適な商品を厳選しました。
| 商品名 | 特徴 | おすすめポイント | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 大正製薬 五苓散 顆粒タイプ | 携帯に便利な顆粒タイプ | 持ち運びやすく、すぐに溶けるため即効性がある | 約1,000円〜(30包入り) |
| クラシエ 五苓散 エキス顆粒タイプ | 高濃度エキス顆粒 | 即効性が高く、むくみや吐き気の解消に効果的 | 約1,200円〜(30包入り) |
| ツムラ 五苓散 顆粒タイプ | 安定した効果のあるツムラ製 | 胃腸の不調を和らげ、アルコールの分解を促進 | 約1,100円〜(30包入り) |
| 大正製薬 五苓散 ドリンクタイプ | 即効性の高いドリンクタイプ | 飲みやすく、すぐに効果を実感できる | 約300円〜(1本) |
これらの商品は、二日酔いの症状を早く緩和するために効果的で、忙しい日常にもピッタリです。自分のライフスタイルや二日酔いの症状に合わせて選びましょう。
選ぶべき市販『五苓散』商品のポイント



『五苓散』を選ぶ際に、どんなポイントを見ればいいの?
市販の『五苓散』商品を選ぶ際、以下のポイントに注意することで、より効果的に使用できます。
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 自分のライフスタイルに合ったタイプを選ぶ | ・顆粒タイプ:外出先でも服用しやすい。 ・ドリンクタイプ:すぐに効果を実感したい方に最適。 |
| 成分と濃度に注目 | エキス顆粒やドリンクタイプは濃度が高く、即効性があります。濃度の高い商品を選べば、短時間で効果を感じやすいです。 |
| 使用シーンに合わせて選ぶ | ・飲み会前:予防目的には顆粒やドリンクタイプ。 ・飲み会後や翌朝:エキス顆粒や濃度の高い商品が効果的。 |
| 信頼できるブランドを選ぶ | ツムラ、大正製薬、クラシエなどのブランドは長年の歴史があり、品質が安定しています。 |
これらのポイントを参考にして、自分の体調に最適な『五苓散』商品を選ぶことが、二日酔い解消の早道です。
漢方『五苓散』の効果を高めるための飲み方のコツと注意点
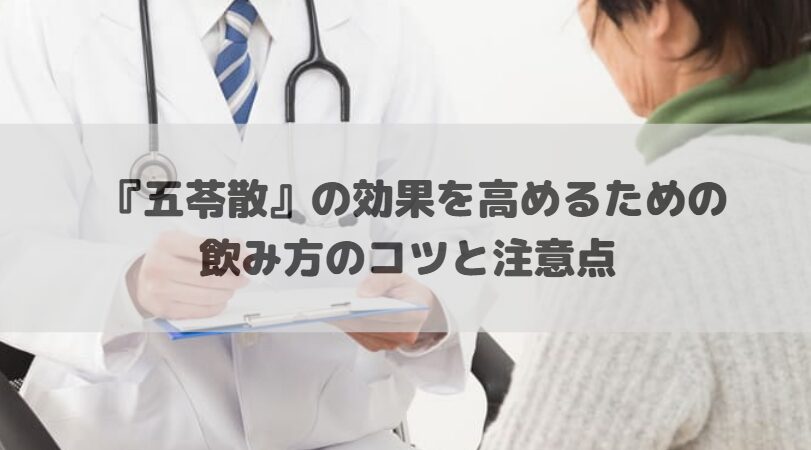
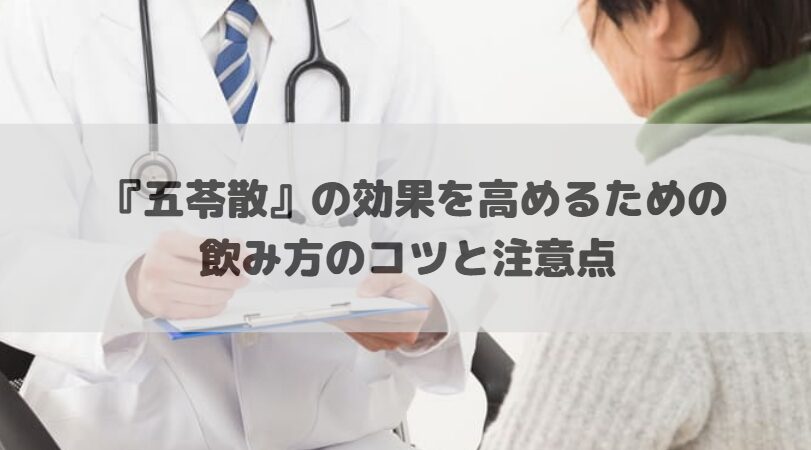



『五苓散』の効果を最大限に引き出すためには、どうやって飲めばいいの?
何か注意するべきことは?
『五苓散』を飲んだだけではなく、その飲み方やタイミングによって効果が大きく変わります。
ここでは、『五苓散』の効果を高めるためのコツや注意点を紹介します。最適な飲み方を実践して、二日酔いをすっきり解消しましょう。
『五苓散』と相性の良い食べ物・悪い食べ物



『五苓散』を飲んでいるときに、どんな食べ物を摂ると効果的?逆に、避けるべき食べ物は?
『五苓散』は、むくみや二日酔いによる不調を和らげる漢方薬ですが、その効果をさらに高めるためには、食事にも気をつけることが重要です。
以下の食べ物は『五苓散』との相性が良く、逆に避けるべき食べ物もあるので、注意しましょう。
【相性の良い食べ物】
| 食べ物 | 理由 |
|---|---|
| 軽めの消化に良い食べ物(おかゆ、スープなど) | 『五苓散』は胃腸の調子を整えるため、軽い食事で胃を労わることが効果的です。 |
| 水分補給ができる食べ物(スイカ、トマト) | 水分補給は二日酔い予防に不可欠です。これらの食材は水分が豊富です。 |
| 消化を助ける食べ物(生姜、ニンニク、レモン) | 体内の循環を促進し、消化を助けるため、『五苓散』と相性が良いです。 |
【相性の悪い食べ物】
| 食べ物 | 理由 |
|---|---|
| 脂っこい食べ物(揚げ物、ファーストフード) | 油分が胃腸に負担をかけ、『五苓散』の効果を弱める可能性があります。 |
| アルコール、カフェインを含む飲み物 | アルコールは『五苓散』の効果を弱め、カフェインは脱水を促進するため控えめに。 |
他の薬と併用する際の注意点



『五苓散』を他の薬と一緒に飲んでも大丈夫?併用する際の注意点は?
『五苓散』は漢方薬なので、他の薬との併用にも一定の配慮が必要です。
基本的には、副作用や相互作用のリスクを避けるために注意が必要です。以下の点に気をつけて、他の薬と併用しましょう。
【併用時の注意点】
| 薬の種類 | 注意点 |
|---|---|
| 西洋薬(例:利尿剤) | 『五苓散』は利尿作用があるため、利尿作用の強い薬と併用すると過度の水分排出が起き、脱水症状や低血圧のリスクが高まります。 |
| 他の漢方薬(例:防已黄耆湯) | 複数の漢方薬を服用する場合は、相互作用により過剰な利尿作用が発生する可能性があります。必ず医師に相談しましょう。 |
| 服用時間の調整 | 他の薬と服用時間をずらすことで、相互作用を避けることができます。『五苓散』と他の薬を同時に飲むことは避けましょう。 |
【医師に相談することをおすすめ】
他の薬を常用している方や健康に不安がある方は、必ず医師または薬剤師に相談し、適切な服用方法を確認してください。
自分の体調や使用中の薬に合わせた『五苓散』の服用が、二日酔いやむくみを改善する効果を最大化します。
まとめ|『五苓散』で二日酔いを早く解消!



「二日酔いが辛い…でも、もう我慢しなくていいんだ!」
二日酔いはつらい症状ですが、『五苓散』をうまく活用することで、早く回復することができます。
ここまでで紹介した内容をしっかり理解し、上手に使えば、翌日をスッキリと過ごすことができますよ。
『五苓散』を活用するポイント
- タイミングを見計らって服用
飲み会前や後、または二日酔いの症状が出始めたときに服用することで、効果を最大化できます。 - 自分に合ったタイプを選ぶ
顆粒タイプやドリンクタイプなど、ライフスタイルやその時の症状に合わせて選びましょう。ドリンクタイプは即効性があり、顆粒タイプは携帯に便利です。 - 生活習慣の改善を合わせて行う
十分な水分補給や睡眠をとることが、回復を早めるカギとなります。『五苓散』の効果をサポートする生活習慣を心掛けましょう。
『五苓散』は二日酔い解消に優れた効果を発揮しますが、選び方や服用タイミングを適切に守ることが大切です。自分の症状に合わせた使い方をすることで、無理なく二日酔いを早く解消できるので、是非取り入れてみてください
参考文献
公的機関・専門機関のウェブサイト:
厚生労働省:eJIM(日本統合医療学会)https://www.ejim.ncgg.go.jp/public/herbs/index.html
国立健康・栄養研究所:「健康食品」の安全性・有効性情報 https://hfnet.nibiohn.go.jp/
日本漢方生薬製剤協会
日本産婦人科学会、日本産科婦人科内視鏡学会、日本女性医学学会(旧日本更年期医学会):https://www.jsog.or.jp/
学術論文データベース:
PubMed:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
Google Scholar: https://scholar.google.co.jp/
書籍:
漢方に関する書籍
- 例:「漢方医学」, 「和漢薬の事典」, 「漢方薬・生薬活用QA」など
薬膳に関する書籍
- 例:「薬膳・漢方検定公式テキスト」, 「薬膳レシピ」など
キノコに関する書籍(茯苓はキノコの一種であるため)
免責事項
本記事は、漢方やメンタルケアに関する一般的な情報を提供するもので、医師の診断・治療に取って代わるものではありません。個々の症状や体質には個人差があり、必ずしも同じ効果が得られるとは限りません。体調に異変を感じた場合は自己判断せず、速やかに医療機関にご相談ください






