
「なんとなく不調が続く…でも病院では異常なし。」
「夏でも手足が冷たい、むくみがひどくて朝起きると顔がパンパン」



「運動してもなかなか痩せない、食事制限をすると体調が悪くなる」
そんな悩み、ありませんか?
漢方薬は「体のバランスを整え、根本から健康をサポートする」という独自のアプローチで、慢性疲労や冷え、ストレスに悩む人に最適!
でも、「即効性がない」「体質によって合わない」などのデメリットも…。
この記事では、漢方のリアルなメリット・デメリット、どんな人におすすめかを徹底解説します!
- 漢方薬と西洋薬の違い
- 漢方薬のメリット・デメリット
- 漢方薬をおすすめする人



KANKAN専属アドバイザーのルナです。
漢方に精通した知見を惜しみなく皆さんにお伝えしていきますね!
メリット・デメリットを説明する前に!そもそも漢方薬と西洋薬の違いは?


漢方薬を検討するとき、「漢方薬と西洋薬って何が違うの?」とのふと疑問に思いますよね。
結論としては、漢方薬と西洋薬は目的が異なります。
| 漢方薬 | 西洋薬 | |
|---|---|---|
| 特徴 | 体全体のバランスを整える | 病気の原因を直接取り除く |
| 即効性 | 遅い(数週間〜数ヶ月) | 速い(数時間〜数日) |
| 持続性 | 体質改善し、長期的に効果が出る | その場の症状を素早く改善 |
| 副作用 | 比較的少ないが、体質によって合わない場合も | 強力な分、リスクも高い |
| 対象 | 慢性的な不調や体質改善 | 急性症状や特定の病気 |
つまり…



・「すぐに治したいなら西洋薬」
・「根本的に体質を改善したいなら漢方薬」 という使い分けがベスト!
漢方薬のメリット:自然の力で体を整える7つの利点
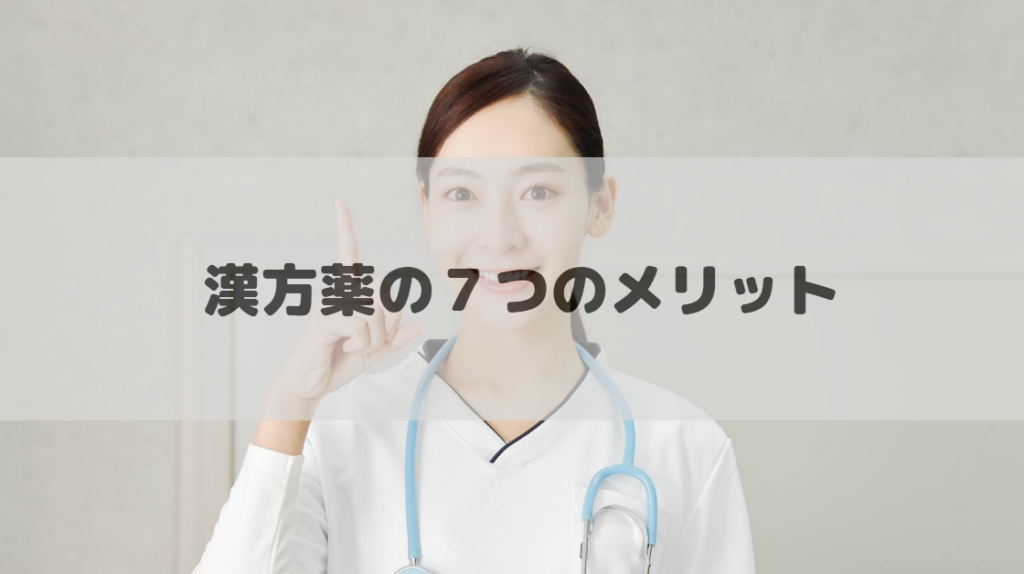
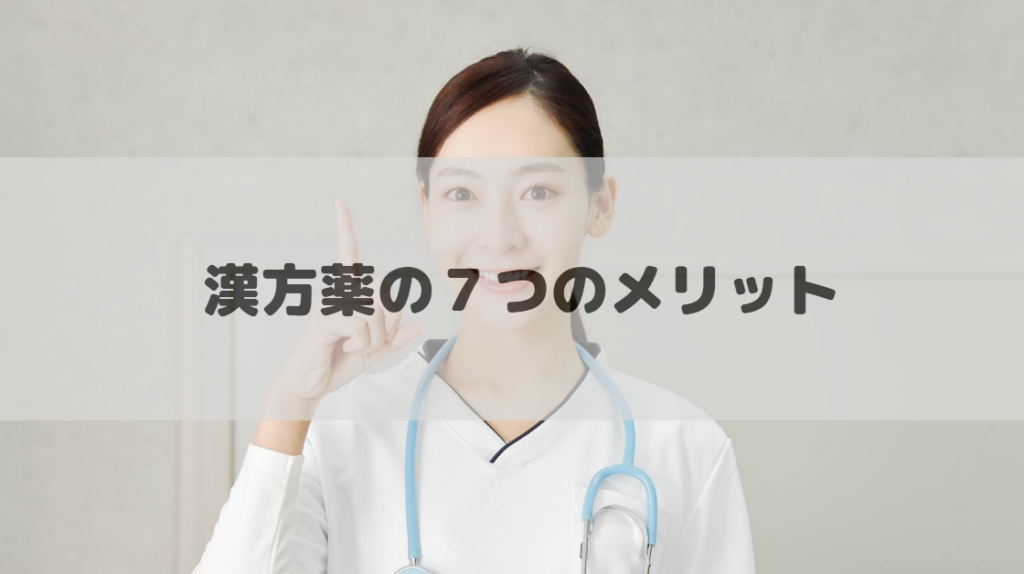
漢方薬は、西洋薬とは異なるアプローチで体の不調を改善する伝統的な医療法です。
では、漢方薬を使うことのメリットを詳しく解説していきます。
| メリット | 具体的な効果 |
|---|---|
| ① 体全体のバランスを整える | 病気になりにくい体を作る |
| ② 副作用が少ない | 長期的に安心して使える |
| ③ 慢性的な不調を改善 | 冷え・便秘・ストレスなどに効果的 |
| ④ 免疫力や自然治癒力を高める | 風邪予防や病後の回復をサポート |
| ⑤ 体質に合わせた処方が可能 | オーダーメイド感覚で薬を選べる |
| ⑥ 美容やダイエットにも効果的 | むくみ、冷え、肌荒れの改善 |
| ⑦ 西洋薬と併用できる | 状況に応じて使い分けが可能 |
1. 体のバランスを整え、根本から健康をサポート
漢方薬は単に症状を抑えるのではなく、「気・血・水」のバランスを整え、体全体の調和を取ることで健康をサポートします。
例えば、冷え性や胃腸の不調など、西洋薬では原因がはっきりしない不調にも効果を発揮します。
- なんとなく疲れやすい、だるい
- 季節の変わり目に体調を崩しやすい
- ストレスで体調を崩しがち
2. 副作用が少なく、体に優しい
西洋薬は即効性がある反面、強い作用とともに副作用も起こりやすいですが、漢方薬は自然由来の生薬を使用するため、比較的副作用が少ないとされています。
ただし、体質に合わない場合や長期間の過剰摂取で影響が出ることもあるため、専門家のアドバイスを受けるのがベストです。
- 西洋薬の副作用が気になる
- 長期間安心して服用したい
- 妊娠中・授乳中でも使える薬を探している
3. 慢性的な不調や体質改善に効果的
漢方薬は、長期的な体質改善に向いています。例えば、冷え性・アレルギー・胃腸虚弱・生理不順など、慢性的な症状に効果を発揮します。
「なんとなく不調」を改善できるのも漢方の魅力。西洋医学では病気と診断されなくても、漢方では「未病」として対処できます。
- 慢性的な冷えや疲れ、便秘に悩んでいる
- 生活習慣を改善しながら、薬の力も借りたい
- 体調を根本から整えたい
4. 自然由来の成分で、免疫力や自然治癒力を高める
漢方薬には、体の免疫力や自然治癒力を高める作用があります。特に、風邪予防や病後の回復に役立つ処方が多くあります。
例えば、「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」は、疲労回復・免疫力向上に効果的で、病後の回復や体力が落ちている人におすすめです。
- 風邪をひきやすい、免疫力が低いと感じる
- 疲れやすく、回復が遅い
- 病気を未然に防ぎたい
5. 個人の体質に合わせたカスタマイズが可能
西洋薬は病名に基づいて同じ薬が処方されますが、漢方薬は一人ひとりの体質や症状に合わせて選ばれるのが特徴。
例えば、同じ頭痛でも、血流が悪いのか、ストレスが原因なのかで処方が変わるため、より適切な治療ができます。
- 西洋薬ではなかなか合う薬が見つからない
- 体質に合った薬を使いたい
- 生活習慣や体調の変化に応じて、柔軟に対応したい
6. 日常のケアや美容にも応用できる
漢方薬は「病気を治すだけ」ではなく、美容やダイエット、ストレスケアにも役立ちます。
例えば、「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」は、血流を良くし冷え性やむくみ改善、「防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)」は脂肪燃焼を促進しダイエットにも効果的です。
- 冷え性やむくみが気になる
- 自然な方法でダイエットをしたい
- ストレスを和らげる方法を探している
7. 西洋薬との併用が可能で、より効果的な治療ができる
「漢方薬 or 西洋薬」ではなく、「漢方薬 × 西洋薬」の併用が最強の選択肢になることもあります。
例えば、風邪の初期に葛根湯を使い、症状が進んだら解熱剤を併用するなど、状況に応じて使い分けることで、より良い効果が得られます。
- 西洋薬だけでは不調が改善しきれない
- 一時的な症状と、体質改善を同時にしたい
- 長期的な健康維持のために、両方を活用したい
漢方薬の3つのデメリットとその対策
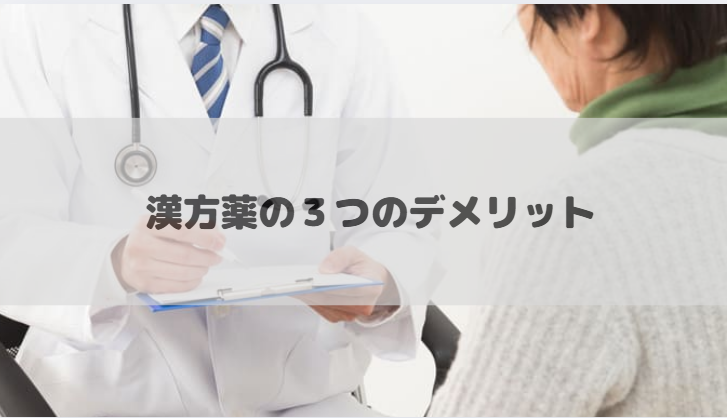
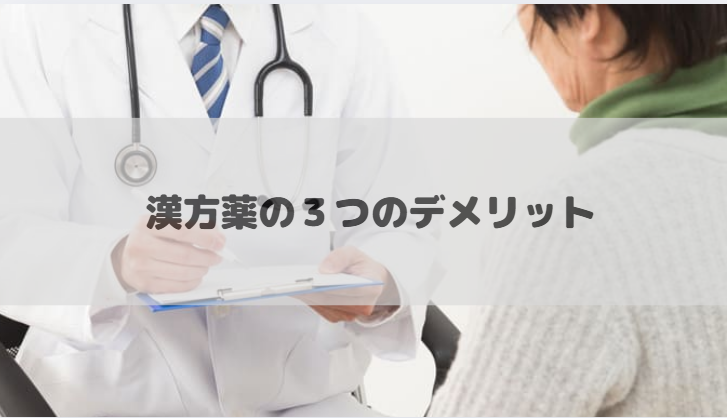
漢方薬には多くのメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットもあります。
ここでは、特に重要な3つのデメリットを解説し、それぞれの対策も紹介します。
| デメリット | 対策 |
|---|---|
| ① 効果が遅い | 西洋薬と併用、生活習慣の改善、即効性のある漢方を選ぶ |
| ② 体質によって合う・合わないがある | 専門家に相談、自分の体質を理解、効果がなければ処方を見直す |
| ③ 味や飲み方が苦手な人がいる | エキス顆粒・錠剤を選ぶ、飲みやすく工夫、飲む習慣をつける |
1. 効果が現れるまでに時間がかかる



「漢方薬を飲んでみたけど、なかなか効かない…」
そう感じたことはありませんか? 漢方薬は根本的な体質改善を目的とするため、西洋薬のようにすぐに症状を抑えるわけではありません。
しかし、これはデメリットである一方、長期的に見ると体調を根本から整えられるというメリットにもなります。
では、この「効果の遅さ」を補う方法を見ていきましょう。
🔹デメリット
- 即効性がないため、短期間で効果を実感しにくい。
- 体質改善を目的とするため、数週間〜数ヶ月かかることが一般的。
- 風邪や頭痛のような急性症状には向かない。
✅ 対策
- 急な症状には西洋薬と併用する(例:風邪の初期には葛根湯、熱が出たら解熱剤)。
- 効果を高めるために生活習慣も見直す(冷え性には漢方+適度な運動や温活を組み合わせる)。
- 効果が出やすい処方を選ぶ(例えば、便秘には即効性が比較的ある「大黄甘草湯」など)。
2. 体質に合わないと効果が出にくい
「同じ症状なのに、友達には効いて自分には効かない…?」
実は、漢方薬は個人の体質に大きく影響を受けるため、同じ症状でも「効く人・効かない人」が出てきます。
例えば、冷えが原因の胃痛と、ストレスが原因の胃痛では、選ぶべき漢方が異なります。
そのため、「なんとなく選んで飲んでみる」のではなく、自分の体質に合った漢方を選ぶことが大切です。
🔹デメリット
- 個人の体質や症状によって、合う・合わないがある。
- 同じ症状でも「冷えが原因」なのか「ストレスが原因」なのかで処方が異なるため、適切なものを選ばないと効果が出ないことがある。
- 自己判断で選ぶと逆効果になる場合もある(例:体が冷えている人が「防風通聖散」を飲むと、さらに冷えが悪化)。
✅ 対策
- 専門家(医師・薬剤師・漢方相談員)に相談して選ぶ。
- 自分の「証(体質)」を知る(例えば、「虚証」なら体力がないタイプ、「実証」なら体力があるタイプ)。
- 短期間試して効果がなければ処方を見直す(2〜3週間で変化がなければ別の漢方を検討)。
3. 味や飲み方に抵抗を感じることがある
「漢方薬って、苦くて飲みにくい…」「煎じるのが面倒…」
漢方薬の独特な味や香りに苦手意識を持つ人は少なくありません。
また、煎じ薬の場合、毎回30分〜1時間かけて作る必要があり、手間がかかるのもデメリットです。
しかし、最近では「錠剤タイプ」や「顆粒タイプ」も増えており、飲みやすくする方法もあります。
🔹デメリット
- 独特の苦味や漢方特有の香りが苦手な人が多い。
- 煎じ薬の場合、手間がかかる(1回分を煮出すのに30分〜1時間かかる)。
- 1日2〜3回飲む必要があるため、飲み忘れやすい。
✅ 対策
- エキス顆粒タイプや錠剤タイプを選ぶ(粉薬よりも飲みやすい)。
- お湯に溶かしてハチミツやショウガを加えると味がマイルドになる。
- 飲むタイミングを決めて習慣化(例えば、朝食後・昼食後・寝る前など)。
メリット・デメリットは分かった!結局、漢方薬はどんな人におすすめ?





「漢方薬ってどんな人に向いているの?」
実は、すべての人に適しているわけではなく、特に相性が良い人の特徴があります。
このような特徴に当てはまる人に、漢方薬はおすすめです。
では、具体的にどんな人が向いているのかを詳しく見ていきましょう!
1. 慢性的な不調に悩んでいる人
「病院に行くほどではないけど、なんとなく体調が悪い…」
そんな**”未病”**の状態にある人には、漢方薬がぴったりです。
🔹漢方薬が向いている慢性的な不調の例
✅ 冷え性(冬だけでなく、夏でも手足が冷たい)
✅ 疲れやすい・だるさが取れない
✅ 胃腸が弱く、すぐに下痢や便秘になる
✅ 生理痛や生理不順がある
✅ アレルギー体質(花粉症・アトピーなど)
なぜ漢方薬が合うの?
- 体の**「気・血・水」**のバランスを整え、不調の根本原因にアプローチできるから。
- 西洋薬では「異常なし」と診断されても、漢方では体質に合った治療ができる。
👉 例えばこんな漢方がある
- 冷え性なら「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」
- 疲れやすい人には「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」
- 胃腸の弱い人には「六君子湯(りっくんしとう)」
2. 体質を根本から改善したい人
「いつも同じような不調を繰り返してしまう…」
このように**「体質的な問題」**で悩んでいる人には、漢方薬が適しています。
🔹こんな悩みのある人におすすめ
✅ 風邪をひきやすい、免疫力が低い
✅ 年中肩こりや頭痛がある
✅ むくみやすい、太りやすい
✅ ストレスで体調を崩しやすい
なぜ漢方薬が合うの?
- 体のバランスを整えて、体質そのものを改善することができるから。
- 西洋薬のように「対症療法(症状が出たら薬を飲む)」ではなく、症状が出にくい体を作ることができる。
👉 例えばこんな漢方がある
- 免疫力を高める「十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)」
- ストレスを和らげる「加味逍遙散(かみしょうようさん)」
- むくみを解消する「防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)」
3. 西洋薬の副作用が気になる人
「西洋薬を飲むと副作用が出やすい…」
そんな人は、漢方薬を試してみる価値があります。
🔹こんな悩みのある人におすすめ
✅ 薬を飲むと胃が荒れる、気持ち悪くなる
✅ アレルギーがあり、西洋薬が合わないことが多い
✅ できるだけ自然な成分のものを使いたい
なぜ漢方薬が合うの?
- 自然由来の成分なので、西洋薬に比べて副作用が少ない。
- 化学合成薬が苦手な人でも比較的安心して使える。
- 長期間の服用が可能で、体に負担をかけにくい。
👉 例えばこんな漢方がある
- 胃に優しい「半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)」
- アレルギー体質の改善に「小青竜湯(しょうせいりゅうとう)」
- ストレス性の胃痛に「桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)」
4. 美容・ダイエット・アンチエイジングを意識している人
「自然な方法で体を整えながら、美容やダイエットにも役立てたい!」
漢方薬は、健康だけでなく美容や体型維持にも活用できます。
🔹こんな悩みのある人におすすめ
✅ 冷えやむくみを解消してスリムになりたい
✅ 肌荒れやニキビを改善したい
✅ 老化を防ぎたい、アンチエイジングしたい
なぜ漢方薬が合うの?
- 体の巡りを良くし、内側からの健康をサポートすることで、美容にも効果を発揮する。
- ダイエット向けの漢方もあり、無理なく体重管理ができる。
👉 例えばこんな漢方がある
- ダイエットに「防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)」
- 美肌を目指すなら「当帰飲子(とうきいんし)」
- むくみ解消には「五苓散(ごれいさん)」
結論:こんな人は漢方薬を試してみて!
✔️ 病院で「異常なし」と言われたけど、なんとなく不調が続く
✔️ 薬を飲むと副作用が出やすい、できるだけ自然なものを使いたい
✔️ 体質を改善して、長期的に健康になりたい
✔️ 美容やダイエットにも役立つ薬を探している
「これ、自分のことかも…?」と思った人は、漢方薬があなたの体質に合う可能性大!
気になる症状があれば、ぜひ一度、専門家に相談してみましょう!
免責事項
本記事は、漢方やメンタルケアに関する一般的な情報を提供するもので、医師の診断・治療に取って代わるものではありません。個々の症状や体質には個人差があり、必ずしも同じ効果が得られるとは限りません。体調に異変を感じた場合は自己判断せず、速やかに医療機関にご相談ください








